5月5日は「こどもの日」として広く知られていますが、元々は古来より続く伝統行事「端午の節句(たんごのせっく)」でした。
今は子どもの健やかな成長や出世を願い、鯉のぼりや鎧兜、五月人形を飾るなど、季節の風物詩として定着しています。
ところで、この行事のルーツや地域ごとの風習にはあまり知られていない興味深い背景があるのをご存知でしょうか?
この記事では、端午の節句の由来とこどもの日の違い、全国各地に伝わる風習の違いについて詳しく解説します。
端午の節句の由来|実は「厄払い」が始まりだった?
現代では「男の子の日」として定着している端午の節句ですが、ルーツをたどると中国の古代習俗にたどり着きます。中国では旧暦5月5日が「五毒日」と呼ばれ、病気や災厄をもたらすとされる日でした。そのため、菖蒲やよもぎなどの薬草を使って邪気を払う風習が生まれました。
この風習は奈良時代に日本へと伝わり、宮中の行事として定着。特に「菖蒲(しょうぶ)」が「尚武(しょうぶ=武を重んじること)」に通じるとして、武家社会において男児の出世と無事成長を願う行事へと変化していきました。
こどもの日は戦後に制定された国民の祝日
一方、「こどもの日」は1948年(昭和23年)に祝日法によって定められた比較的新しい国民の祝日で、「こどもの人格を重んじ、こどもの幸福をはかるとともに、母に感謝する日」とされています。男女問わず、すべての子どもとその家族に向けた祝日です。
なぜ同じ日になったのか?
端午の節句は古くから旧暦の5月5日に行われていましたが、明治時代の暦の改正により新暦に合わせて「5月5日」に固定されました。そして戦後、「こどもの日」も同じ5月5日に設定されたことで、両者が同日に行われるようになりました。
このように、端午の節句は歴史ある季節行事であり、こどもの日は近代に生まれた祝日という違いがあります。現在では、両方の意味を込めて鯉のぼりを飾ったり、柏餅を食べたりする家庭が多く見られます。
全国に広がる端午の節句の風習|地域の文化が色濃く反映
端午の節句には、地域によって多様な風習や食文化が存在します。代表的な例を紹介します。
鯉のぼり|立身出世を象徴する風習
江戸時代の町人文化から生まれた鯉のぼりは、鯉が滝を登る伝説「登龍門」にちなんで、出世と成功を願う意味があります。関東地方を中心に全国で見られ、空高く泳ぐ鯉の姿は春の風物詩となっています。
五月人形・鎧兜|災厄を受け止める“身代わり”の意味
武士の文化が色濃く残る五月人形や鎧兜は、子どもを災難から守る“身代わり”の意味を持ちます。飾る形は地域によって異なり、兜飾りや武者人形など多彩です。
ちまきと柏餅|東西で異なる節句スイーツ
東日本では柏餅、西日本ではちまきが主流ですが、両方食べる地域もあります。
- ちまき:中国から伝来。もち米を笹や茅の葉で包んで蒸した保存食で、邪気払いの意味がある。
- 柏餅:日本独自の風習で、柏の葉が「子孫繁栄」の象徴とされる。
菖蒲湯|健康と無病息災を祈る入浴習慣
菖蒲の香りが邪気を払うと信じられ、端午の節句には菖蒲を入れた「菖蒲湯」に入る風習があります。葉の形が刀に似ていることから、「尚武」の精神とも重ねられます。
地域限定のユニークな風習も!
端午の節句は全国共通の行事でありながら、各地にはその土地ならではの独自の風習が残っています。
- 東北地方:紙兜や武者絵を飾る風習があり、民芸の要素が強く見られます。
- 四国地方:ちまきの代わりに「笹巻き」を作って食べる地域もあります。
- 九州地方:鹿児島など一部地域では「節句相撲」と呼ばれる行事があり、男の子たちが力を競い合います。
まとめ:端午の節句は家族の願いが込められた日本の伝統文化
端午の節句は、古代中国の厄除け行事に端を発し、時代や文化の変遷の中で「子どもの成長を願う日」へと発展しました。地域ごとの風習や食べ物に触れることで、この行事がいかに家族や社会に根付いてきたかを実感できるはずです。
ぜひその背景や地域色に思いを馳せながら、家族とともにこの日を楽しんでみてはいかがでしょうか。
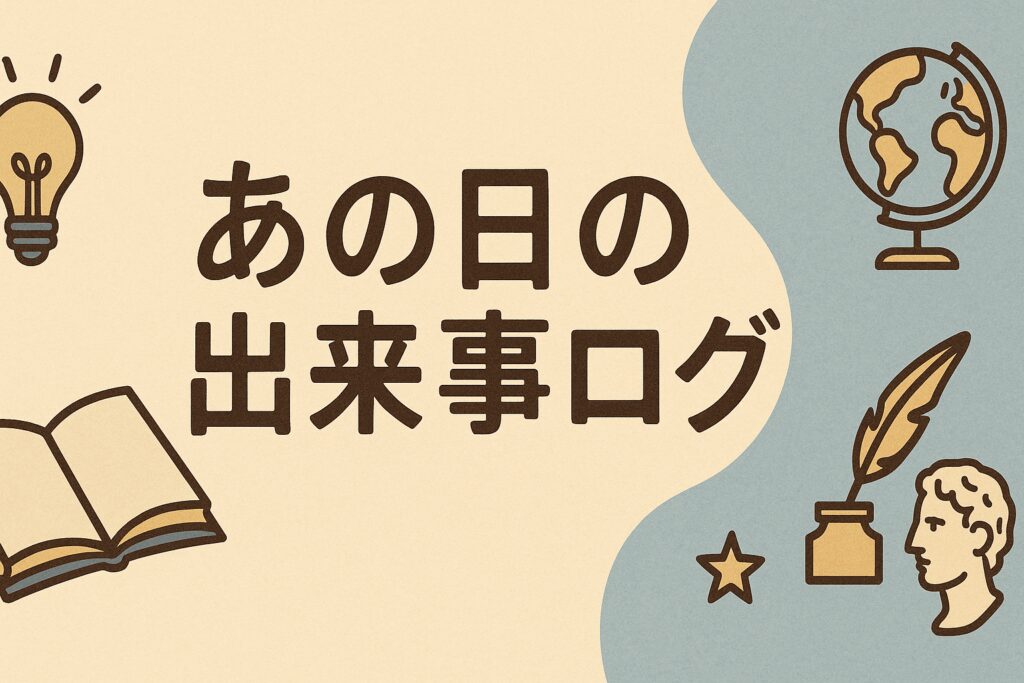
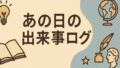
コメント