2014年、アメリカ・ウィスコンシン州で、12歳の少女2人が同級生を森へ連れ込み、19回も刺すという衝撃的な事件が発生しました。
動機は、「スレンダーマンに認められるため」。ネット上で創作された都市伝説の存在が、なぜ現実の凶行につながったのでしょうか。
スレンダーマンとは何か?
スレンダーマンは、2009年にホラーフォーラム「Something Awful」で行われたフォトショップコンテストから誕生した架空の怪人です。
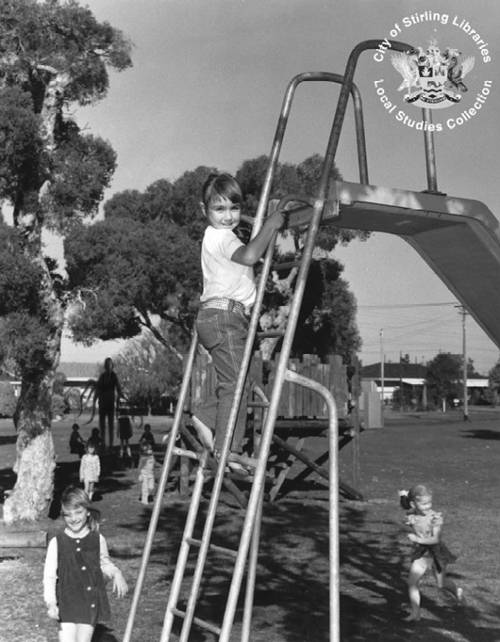
黒いスーツを着て、異様に背が高く、顔のない人影――そんな姿で描かれるスレンダーマンは、森や子どものそばに現れるという設定とともに、多くのユーザーによって画像やストーリーが投稿され、ネット文化の中で急速に広まっていきました。
ネット文化への浸透
スレンダーマンは単なるネット上の創作キャラクターにとどまらず、YouTube、Creepypasta、Reddit、Tumblrといったオンラインコミュニティで語り継がれ、独自のサブカルチャーを築いていきました。
2012年にはホラーゲーム『Slender: The Eight Pages』が登場し、プレイヤーを追い詰めるスレンダーマンの恐怖が大きな話題に。以後、映画化やテレビ番組での特集も相次ぎ、「スレンダーマン」はネットから飛び出してリアル世界の象徴的存在になっていきます。
こうした文化的広がりが、「もしかしたら実在するのでは」という幻想を一部の若者に植えつけ、フィクションと現実の境界をあいまいにする要因となったのです。
2014年 ウィスコンシン州刺傷事件
2014年5月31日、ウィスコンシン州ワウケシャにある森の中で、12歳の少女2人が同級生を19回も刃物で刺すという事件が起きました。
加害少女たちは、スレンダーマンの存在を信じており、「彼に仕える代理人になるためには誰かを犠牲にする必要がある」と考えていたと供述しています。スレンダーマンに従えば、自分たちも傷つかずに済むという信念からの犯行でした。
なぜ信じ込んでしまったのか?
この事件の背景には、フィクションと現実の境界が曖昧になる心理的メカニズムが存在します。加害者の一人は後に統合失調症と診断されており、幻覚や妄想によってスレンダーマンの実在を確信していたといいます。もう一人もその信念に同調し、共犯者となりました。
2人はネット上でスレンダーマンに関する情報を熱心に集めており、彼の住む場所とされる「ナショナルフォレスト」へ向かう計画まで立てていました。彼女たちは、物語をただ読むのではなく、“生きる現実”として受け入れていたのです。
被害者とその後
被害にあった少女は、命に関わる重傷を負いながらも、森の中から自力で道路へ這い出て救助を求め、奇跡的に一命を取りとめました。手術とリハビリを経て社会復帰を果たしましたが、心身に深い傷を残すこととなりました。
加害者2人は精神鑑定と裁判の結果、成人と同様の刑事責任を問われ、それぞれ精神病院への長期収容処分が下されました。彼女たちの精神状態、家庭環境、そしてインターネットの影響が、事件の背景として多角的に議論されています。
社会が受けた衝撃
この事件は、「ネット上のフィクションが現実の暴力につながり得る」という点で、アメリカ国内だけでなく世界的に報道されました。保護者や教育関係者にとっては、子どもたちのネット利用の危うさを再認識させる契機となり、また精神疾患と未成年犯罪にどう対応するかという法的課題も提起されたのです。
なぜ「虚構」が「現実」になるのか
スレンダーマンの物語は、誰でも参加できるネット文化の中で次々と拡張され、リアルな存在のように錯覚されていきました。SNSや動画サイトの拡散力が、それをさらに強化していったのです。
この事件は、フィクションの影響力と向き合う必要性を社会に突きつけました。情報との付き合い方、創作と現実の区別、そして「信じる」という行為の危うさ。スレンダーマンは、単なるモンスターではなく、情報社会が生み出した“影”の象徴とも言えるでしょう。
まとめ
創作として生まれた「嘘」が、信じた者にとって「真実」となったとき、現実の悲劇を引き起こすことがあります。
ネットという無限の舞台で生まれ語られる怪異の物語は、ときに人の心を支配し、現実へと浸食していきます。私たちは今こそ、「物語」と「現実」の境界をどれだけ意識できているか、自問する必要があるのかもしれません。





コメント