キャッシュレス決済が普及し、現金の出番が減った現代。そんな中、SNSでは「1円玉はいらないのでは?」という声もちらほら見られます。実際、1円玉1枚をつくるのに約3~3.6円かかるといわれています。
こうした議論の背景には、かつて同じように「使われなくなった通貨の整理」が行われた歴史があります。それが1953年に施行された「小額通貨整理法」です。
今回は、銭(せん)や厘(りん)といった、今では見かけない通貨単位がなぜ姿を消したのか。その背景や私たちの暮らしに与えた影響をわかりやすく解説します。
小額通貨整理法とは?
正式名称:小額通貨の整理及び支払金の端数計算に関する法律
1953年(昭和28年)7月に制定されたこの法律は、1円未満の通貨単位(銭・厘)を廃止し、支払いの端数処理ルールを統一することを目的に施行されました。
なぜ1円未満の通貨が廃止されたのか?
実生活で使われなくなった
1銭=0.01円、1厘=0.001円。戦後のインフレーションにより、これら小額通貨の価値は急激に下落し、ほとんど使われない“形だけの通貨”になっていました。
発行コストのムダ
使われないにもかかわらず、通貨を発行・管理するには莫大なコストがかかります。合理化が求められていた時代には、見直しが急務でした。
支払い計算が非効率だった
たとえば「19円53銭」といった取引では、わずかな端数があるだけで会計や計算が煩雑になります。商取引の現場では、このわずかな非効率が大きな手間になっていたのです。
小額通貨整理法で変わったこと
1953年12月31日をもって、以下の通貨・制度が正式に廃止・変更されました。
銭・厘などの1円未満通貨の廃止
1円未満の通貨(銭・厘)は法定通貨としての効力を完全に失いました。現在では記念的・収集用にしか流通していません。
古い1円硬貨(黄銅貨)も使用不可に
現在のアルミ製の1円玉ではなく、それ以前の黄銅製1円玉も、同様に使えなくなりました。
支払い時の端数処理が統一された
現金での支払い時、1円未満の端数は次のように処理されることになりました。
- 50銭未満 → 切り捨て
- 50銭以上 → 1円に切り上げ
これにより、実生活で「銭」「厘」を気にする必要はなくなりました。
生活に与えた影響とは?
小額通貨整理法は、当時の社会や日常生活にもさまざまな影響を与えました。
レジでの会計がラクになった
小額通貨の廃止で、釣銭計算が大幅に簡素化されました。商店や百貨店などでは、業務効率の向上にもつながりました。
インフレの心理的な抑制
目に見えて価値が薄れていた銭や厘の廃止は、「お金の価値が保たれている」という印象を与え、インフレへの心理的な抑制効果があったとされています。
古銭としての新たな価値
廃止された銭・厘の硬貨や紙幣は、現在ではコレクター市場で高値がつくことも。状態や年代によっては、数千円〜数万円の価値になることもあります。
まとめ:今の通貨制度はこうしてできた
私たちが「1円単位」で買い物をするのが当たり前になったのは、合理化と経済の再建を目指した政策の成果でした。
「小額通貨整理法」は、単なる制度変更ではなく、戦後日本の経済を支える大きな転換点だったのです。
今では使われなくなった「銭」や「厘」。もしご自宅に眠っている古銭があれば、それは時代を映す“証人”かもしれません。
ちなみに旧札や旧貨幣は今でも額面通り、通用するみたいですよ。→ その他有効な銀行券・貨幣
参考リンク
- 日本銀行 1円未満のお金が使えなくなったのはいつからですか?:https://www.boj.or.jp/about/education/oshiete/money/c24.htm
- 衆議院 法律第六十号(昭二八・七・一五):https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_housei.nsf/html/houritsu/01619530715060.htm
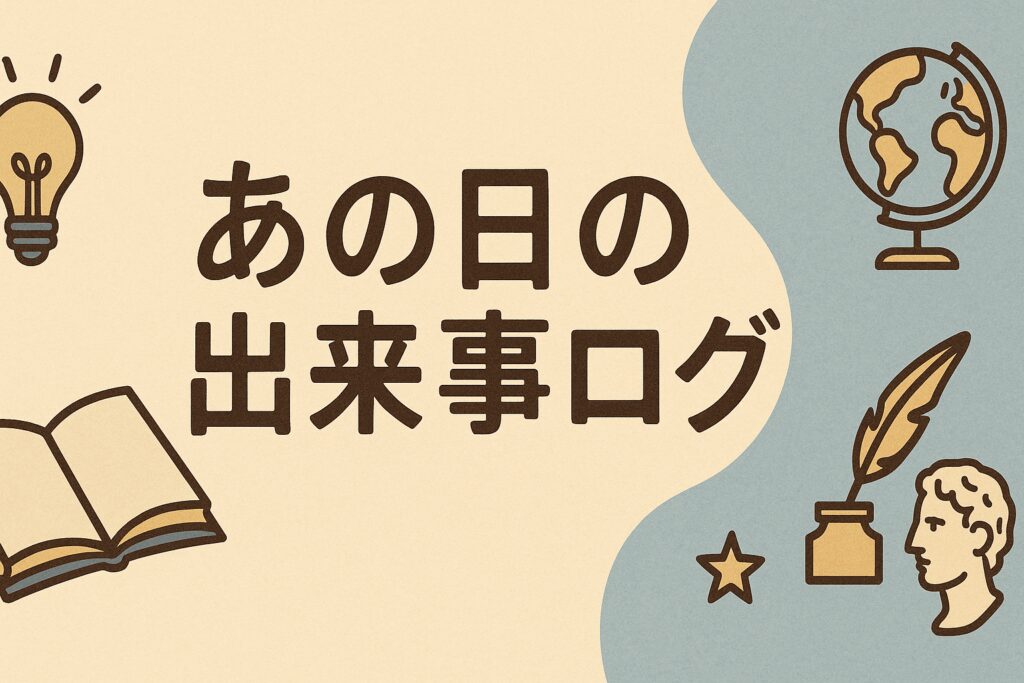
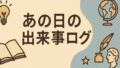
コメント