「もうこれで一巻の終わりだ」──そんなふうに使われるこの慣用句、なぜか聞くだけで絶望的な響きを感じますよね。
でも、よく考えてみると「一巻の終わり」って、いったい何の“巻”で、なぜその“終わり”がそんなに重大な意味を持つのでしょうか?
今回は、よく耳にするけれど、改めて考えるとちょっと不思議なこの表現の由来を、じっくり掘り下げてみます。
無声映画時代の「一巻の終わり」
大正から昭和初期、まだ映画に音声がついていない無声映画の時代。当時の映画フィルムは、物理的な「巻」として管理されていました。一本目を「一巻」、二本目を「二巻」と数え、それぞれが独立したリールに巻かれていたのです。
映画館では、活動弁士(通称:弁士)と呼ばれる専門の解説者が、スクリーンの横に立って映画の内容を観客に語って聞かせていました。そして一巻分の上映が終わると、弁士が決まり文句のように「一巻の終わり」と観客に告げるのが慣例だったのです。
この「一巻の終わり」は、単純に物理的なフィルムの区切りを意味していました。つまり、最初は今でいう「第一部完」のような、ニュートラルな意味合いだったわけです。
意味の変化:なぜ「絶望的」になったのか
しかし時代が流れるにつれて、この表現は次第に重い意味を帯びるようになりました。映画のクライマックスで「一巻の終わり」と告げられることが多かったため、「すべてが終わる」「後戻りできない決定的な瞬間」というニュアンスが定着していったのです。
現代では、単なる終了を表すのではなく、むしろ「望みが絶たれる」「破滅的な結末」といった、ドラマチックで悲劇的な状況を表現する際に使われることがほとんどです。
「試験に落ちたらもう一巻の終わりだ」 「この失敗で、彼のキャリアは一巻の終わりとなった」
このように、単純な終了ではなく、絶望や諦めを含んだ「完全なる終焉」を表現する慣用句として定着しています。
現代でも生きる映画由来の表現力
興味深いのは、映画が完全にデジタル化された現代でも、この古い映画用語が生き続けていることです。フィルムの「巻」という概念すら知らない世代にも、「一巻の終わり」という表現の持つドラマチックな響きは確実に伝わります。
これは言葉の持つ音韻や語感が、元々の意味を超えて独自の表現力を獲得した好例と言えるでしょう。映画館の弁士が告げた一言が、100年近い時を経て、現代の日本語に深く根付いているのです。
まとめ
「一巻の終わり」は、無声映画時代の映画館から生まれ、時代と共に意味を変化させながら現代まで生き続けている興味深い慣用句です。
単なる終了から絶望的な終焉へと意味を深めたこの表現は、日本語の豊かな表現力を物語る一例と言えるでしょう。
次にこの言葉を耳にした時は、かつて映画館で弁士が告げた一言の歴史を思い出してみてください。きっと、その言葉の重みがより深く感じられるはずです。
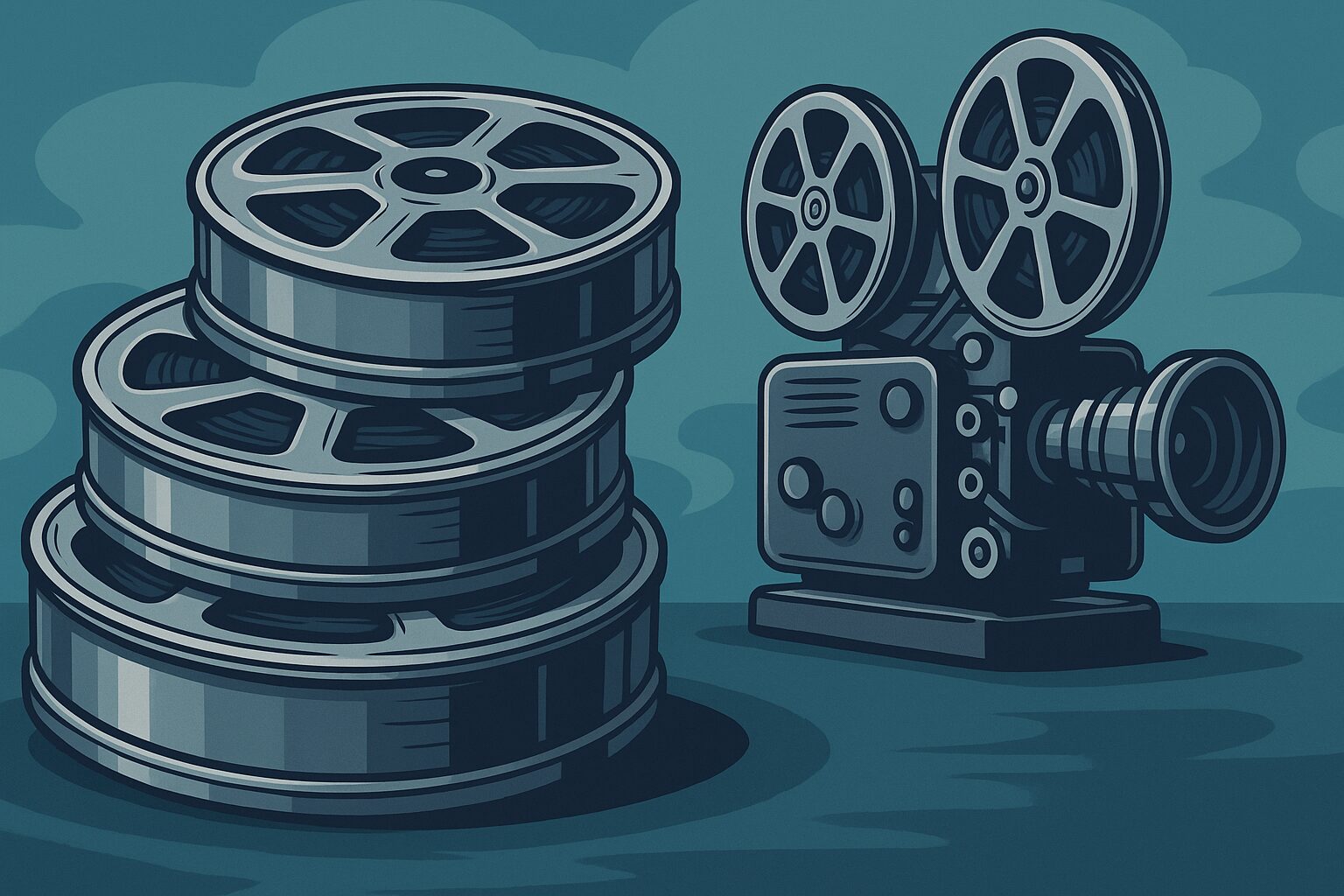


コメント