映画館に一歩足を踏み入れた瞬間にふわっと香る、あの甘じょっぱい香り。
今でこそ「映画といえばポップコーン」という組み合わせは当たり前になっていますが、その背景には意外な歴史と、映画館側のしたたかな戦略が隠されていました。
映画館に食べ物?最初はNGだった時代
映画が誕生したばかりの頃、映画館は「上品な大人の社交場」でした。
サイレント映画の時代には、観客は演劇を鑑賞するような静粛な雰囲気で映画を楽しんでおり、飲食は禁止されていたところも多かったのです。
当時の映画館にはカーペットが敷かれ、クラシック音楽が流れ、観客は正装して出かけることもあるような、ある意味で格式のある場所でした。
ポップコーンは“庶民の味方”から始まった
ポップコーンの歴史は、実はとても古く、アメリカ大陸の先住民の時代までさかのぼります。
19世紀にはすでに、縁日やサーカスなど人が集まる場所で手軽に食べられるスナックとして親しまれていました。
そんなポップコーンが映画館と結びつく大きなきっかけとなったのが、1929年に始まった世界恐慌です。
経済が冷え込む中でも、映画館は比較的安価な娯楽として人気を集めました。
その人の波に目をつけたのが、映画館の外でポップコーンを売る露天商たち。ポップコーンは安くてボリュームもあり、映画を観に来た人々に大ウケだったのです。
「これはチャンスだ」映画館側の戦略的転換
当初、映画館の経営者たちはポップコーンの持ち込みに反対でした。館内が汚れるし、においも強い。
でも、外でポップコーンがどんどん売れていくのを見て、彼らはこう思ったことでしょう。

自分たちで売れば、利益になるのでは?
結果的に、ポップコーンの販売はチケット以上の利益を生み出す“ドル箱”に。
原価が安く、日持ちして、大量に作れる。しかも塩気があるので喉が渇きやすく、ドリンクの売上まで伸ばしてくれる。
ポップコーンは、映画館のビジネスモデルを支える重要な柱となっていきました。
技術の進歩と戦争が追い風に
1930年代には、映画館内でもポップコーンをその場で作れるマシンが登場。
作りたての香ばしい香りは、お客さんを惹きつける“嗅覚マーケティング”としても有効でした。
さらに、第二次世界大戦中には砂糖が配給制となり、キャンディのような甘いお菓子が不足。
一方で、塩とバターだけで作れるポップコーンは代替スナックとして人気が急上昇。
時代背景も相まって、映画館でのポップコーンはますます“定番の味”となっていきました。
日本の映画館とポップコーン文化の違い
さて、日本ではどうでしょうか。
アメリカほど「映画といえばポップコーン!」という文化は根付いていませんでした。
昭和〜平成初期の名画座などでは、映画中に食べ物を広げることに抵抗感があり、ポップコーンも“あるにはある”程度の存在感。
しかし、シネコン文化が発展した1990年代以降、ポップコーンは“映画館体験”の一部としてブランディングされ、日本独自のフレーバー展開(キャラメル、バターしょうゆ、チーズなど)もあって、映画館の定番スナックとしてしっかりとポジションを確保しています。
サブスク時代でも変わらない“映画館の味”
最近ではNetflixやAmazon Primeといったサブスクサービスが普及し、自宅で映画を楽しむ人も増えました。
しかし、どれだけ映像技術が進化しても、「映画館で観る」という体験は特別なもの。
そしてその“特別感”をさらに高めてくれるのが、やっぱりポップコーン。
自宅ではなかなか再現できないあの香りと味が、映画館を訪れる理由の一つではないでしょうか。
ポップコーンは、映画館という非日常空間を構成する重要なピース。
サブスク全盛の今だからこそ、わざわざ映画館に行く価値を支える“体験のスパイス”なのかもしれません。
ポップコーンは映画のもうひとつの主役
こうして振り返ると、ポップコーンが映画館の定番になったのは偶然ではなく、時代の流れと工夫の積み重ねによるもの。
安価でおいしく、香りで気分を高め、ドリンクの売上もアップさせる──こんな優秀なスナック、ほかにないかもしれません。
次に映画館でポップコーンを手にするときは、ただの“おやつ”ではなく、そんな背景にも少し思いを馳せてみてはいかがでしょうか?

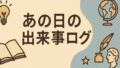
コメント