過去のこの期間、世の中では何が起きていたのでしょうか?20年前・15年前・10年前・5年前の出来事を振り返ってみます。日々のニュースと照らし合わせて、過去の出来事がどのように現在につながっているのか見えてくるかもしれません。
2005年(平成17年)10月21日~10月31日の出来事
【国内】ディープインパクトが菊花賞を制して牡馬クラシック三冠を無敗で達成
2005年10月23日に京都競馬場で行われた菊花賞(日本のクラシックレースの最終戦)で、ディープインパクトが勝利。同馬は皐月賞・東京優駿(日本ダービー)・菊花賞を制して牡馬クラシック三冠を達成しました。ディープインパクトは当時無敗での三冠達成となり、無敗での三冠は1984年のシンボリルドルフ以来21年ぶり、史上2頭目の快挙となりました。
ディープインパクトはデビューから連勝を続け、スピードと持久力を兼ね備えた能力でクラシック戦線を圧倒しました。この日の京都競馬場には観客が押し寄せ、単勝オッズは1.0倍(100円元返し)。多くの期待に応えての勝利となりました。三冠達成後も天皇賞(春)・宝塚記念・ジャパンカップ・有馬記念と勝利を重ね、史上3頭目(当時)の中央競馬GI7勝の最多タイ記録を達成しました。
ディープインパクトは種牡馬としても大成功を収め、日本の競馬界に多大な影響を与えました。産駒は数多くの重賞勝ち馬を輩出し、後進世代への影響力を残しました。
【国際】パリ郊外での感電死を契機にフランス全土で暴動が発生
2005年10月27日にパリ北東部近郊で、警察の追跡を恐れて変電設備に逃げ込んだ若者2人が感電死する事件が発生しました。この出来事をきっかけに、既に蓄積していた若者の失業・差別・警察対応への不満が一気に噴出し、パリを中心にフランス全土で暴動が連鎖的に発生しました。若者たちによる車両や建物の放火、商店の略奪、治安部隊との衝突が続き、数千台の車両焼失や多数の逮捕者が出ました。(2005年パリ郊外暴動事件)
暴動前から、フランスの一部郊外では若年失業、社会的排除、移民や少数派への構造的差別が問題となっており、警察と住民の間の緊張が高まっていました。事件後、当時の内相(後に大統領となるニコラ・サルコジ)は若者を厳しく非難する発言をし、これが火に油を注ぐ形で騒乱はさらに拡大しました。
暴動は数週間にわたり継続し、フランス政府は非常事態宣言を含む厳しい治安対応で鎮圧を図りました(非常事態宣言は11月にかけて適用されました)。事態はフランス社会における格差・統合政策・警察改革の必要性を浮き彫りにし、以後の都市政策や社会統合プログラム、警察の対応方針に影響を与えました。
2010年(平成22年)10月21日~10月31日の出来事
【国内】羽田空港の再国際化:D滑走路・新国際線ターミナル(現在の第3ターミナル)とアクセス新駅が供用開始
2010年10月21日、長らく国内線専用空港として運用されてきた東京国際空港(羽田空港)で、再国際化の一環として4本目の滑走路にあたる「D滑走路」と新たな国際線ターミナル(当時の新国際線ターミナル、現在の第3ターミナル)が供用を開始しました。これに伴い、東京モノレールには「羽田空港国際線ビル駅」が、京急空港線には「羽田空港国際線ターミナル駅」(いずれも現・羽田空港第3ターミナル駅)が開業し、都心と空港を結ぶアクセスが強化されました。
背景として首都圏の国際航空需要増加と、成田空港への過度な集中を是正する方針を受けて、政府と羽田空港の再整備計画が進められていました。D滑走路と国際線ターミナルの整備は、深夜早朝発着制限の緩和や国際便の受入拡大を見据えた戦略的なインフラ投資の一部でした。
羽田の再国際化は短期間で効果を生み、国際航空路線の増加やLCC(格安航空会社)を含む多様な航空サービスの拡充を促しました。都心からの利便性向上は観光・ビジネス需要を押し上げ、成田との補完・競争構造にも変化を与えました。一方で、深夜や早朝の騒音問題や周辺地域の交通集中への対処、国際線増便に伴うセキュリティ・入国管理の強化など運用面での課題も生じ、以後の空港運営・都市計画に継続的な影響を与えました。
【国際】上海万博(Expo 2010)の閉幕
2010年10月31日、上海万博(World Expo 2010)は182日間の会期を終えて閉幕しました。万博は「都市と人間—都市生活をよりよくするために(Better City — Better Life)」をテーマに、世界から多くの参加国・企業が出展し、数千万人規模の来場者を集める大規模な国際交流の場となりました。
中国の急速な都市化と経済成長を世界に示す場として、上海市と中国政府は大規模な再開発とインフラ投資を万博招致の中核としました。会場周辺の交通整備・都市改造は長期計画と連動して実施されました。
閉幕後、万博は上海の都市ブランド向上と観光振興に寄与し、会場や周辺地域のインフラ(道路、地下鉄、空港アクセス、再開発用地)は都市開発の資産となりました。一方で、会期中・後の維持管理費用、会期効果の持続性、用地の恒久利用計画については評価が分かれ、都市計画上の課題として議論が続き、2025年時点では上海を含め中国の不動産バブルが崩壊したとの見方もされています。
国際的には、上海万博は中国のソフトパワー発揮と国際イメージ戦略における重要な成功例として、以後の大規模イベント招致・運営の参考点になりました。
2015年(平成27年)10月21日~10月31日の出来事
【国際】ヨーロッパ難民・移民危機、漂着死体や大量到着を受けた緊急協議と対策論議
2015年10月下旬、地中海経由で欧州へ到達を試みる難民・移民の大規模流入がピークに達し、数多くの漂着死体や船舶事故が報じられたことを契機に、EU加盟国や国際機関が緊急の協議を行いました。国連難民高等弁務官事務所(UNHCR)や国際移住機関(IOM)は、10月だけでヨーロッパに到着した海上移民が大幅に増え、2015年は地中海での死者数が記録的になった年であると報告しました。これらの悲劇は、単に救援の即時強化を求めるだけでなく、欧州の国境管理、シェンゲン協定の運用、加盟国間の受け入れ分担、ならびにトルコなど周辺国との外交的な協働(後のトルコ-EU合意へとつながる協議)を巡る大規模な政策議論を引き起こしました。(2015年欧州難民危機)
2011年以降のシリア内戦やアフリカ各地の紛争・貧困、並びに密航業者の横行により、2015年前半から海上ルートで欧州に向かう移民が急増しました。特に2015年春〜秋にかけて複数の大きな船舶災害が相次ぎ、映像と数千人規模の移動が国際社会の注目を集めました。10月はトルコ→ギリシャルートへの移動が激増した時期であり、数日のうちに大量の到着・複数の沈没事故が重なりました。
2015年の夏〜秋の事態を踏まえ、EUは域内での対応強化、加盟国間の一時的分担協定、海上救助の枠組み見直し、ならびにトルコとの移民管理協議(2016年のトルコ-EU合意へ繋がる一連の取り組み)を進めました。また、欧州内での移民統合政策や国境管理方針に関する国内政治の議論は活発化し、結果として各国の移民受け入れ・国境管理の政策転換を促しました。国際人道・人権団体は「命を守る救助の強化」と「根本原因への国際的取組み」の必要性を繰り返し訴えました。
【国内】東京都日野市三沢の緑地斜面で小4男児が遺体で発見された事件
2015年10月26日夜、東京都日野市三沢の小高い緑地(地元で「高幡山」と呼ばれる場所)で、小学4年生の男子児童(10歳)が首をつった状態で発見されました。遺体は全裸で、両手・両足がひもで縛られており、衣服は近くに置かれていたと報じられました。警視庁は現場の状況や目立った外傷がないことなどから当初は自殺の可能性が高いとみて捜査を進め、遺体発見当初は自殺と事件の両面で調べている旨が報道されました。被害児童の家族は当初、事件性を疑う声も出しており、報道段階で関係者の証言や動機の解明が注目されました。
当日、児童は午前に家を出た後に帰宅せず、心配した家族が通報して行方が捜索されていました。夕方以降の捜索で、夜間に緑地の斜面で遺体が見つかりました。遺体の状態が異様であったため、報道では一時的に事件性が強く疑われる場面もありましたが、警察は現場の状況証拠を踏まえて慎重に鑑定・捜査を行ったとされています。
捜査では当初「自殺の可能性が高い」との見方が報じられましたが、親族など一部関係者からは疑問の声も上がり、引き続き詳細な鑑識・事情聴取が行われました。メディア報道やネット上では、あまりの不可解さに憶測が拡散した時期もあったため、警察は事実関係の慎重な整理と公表を進める必要があるとされました。
当時のネット上では様々な憶測や議論も見られました。(※掲示板ログ)
2020年(令和2年)10月21日~10月31日の出来事
【国内】コントレイルが菊花賞勝利で史上初の父子無敗クラシック3冠達成
2020年10月25日、京都競馬場で行われた第81回菊花賞(GⅠ)で、福永祐一騎手騎乗のコントレイルが優勝し、同馬は皐月賞・東京優駿(日本ダービー)・菊花賞を制して日本競馬の牡馬クラシック三冠を達成しました。父ディープインパクトに続く父子での三冠達成、かつ無敗での三冠制覇は史上3頭目という記録的快挙となりました。
コントレイルは2019年のホープフルステークスなどで頭角を現し、3歳シーズンに入って皐月賞と日本ダービーを順当に勝利していました。長距離の菊花賞では持久力が問われましたが、安定した末脚と福永騎手の好騎乗で勝利を収めました。
この勝利は父子での無敗三冠というドラマ性も相まって競馬ファンやメディアで大きく報じられ、競馬界における血統の重要性を改めて示しました。
【国内】菅義偉首相が2050年カーボンニュートラル目標を表明
2020年10月26日、菅義偉首相は第203回臨時国会での所信表明演説において、「2050年までに温室効果ガスの排出を実質ゼロにする(カーボンニュートラル)」ことを宣言しました。これは日本の長期的な環境政策と産業政策の大転換を示す重要な方針表明として受け止められました。
欧州を中心とした主要国や国際社会が脱炭素目標を掲げる中で、日本も国際的責務と産業競争力を見据えて方向性を明確化する必要がありました。国内では産業界や自治体、消費者の反応を踏まえつつ、グリーン技術・再生可能エネルギーへの投資拡大や規制設計が求められていました。
宣言を受けて政府は具体的な政策パッケージの検討を進め、長期の産業構造転換やエネルギー供給の再編(再エネ導入、石炭火力の取扱い、カーボンリサイクル等)に関する議論と実行計画の策定が進みました。企業側でもESG投資や脱炭素戦略の採用が加速し、国際的な気候外交の場でも日本の目標表明が注目されました。

【国際】2020年10月下旬、 世界的なCOVID-19の再拡大
2020年10月下旬には、欧州や米国を中心に新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の再拡大(いわゆる「第2波/秋冬波」)が顕著になり、多くの国で日次感染者数や入院者数が急増しました。これにより各国は再び行動制限や飲食店の営業時間短縮、階層別の地域制限などを導入し、医療体制の逼迫や経済対策の必要性が緊急課題となりました。
夏季に一旦落ち着いた地域でも、行動緩和や屋内活動の増加、季節性要因により秋以降に感染が再拡大しました。検査体制の強化や接触追跡体制の整備が進んだ一方で、新規感染者急増は保健医療資源の逼迫と社会活動の再制限を招きました。
再拡大の波は冬期にかけて世界各地で続き、ワクチン承認・配布の期待と並行して、各国の医療対応・行動制限・経済支援策が繰り返し調整されました。秋以降の感染拡大は、パンデミック収束までの長期戦を示すものとなり、公衆衛生の強化や社会的安全網の重要性を強調する契機となりました。
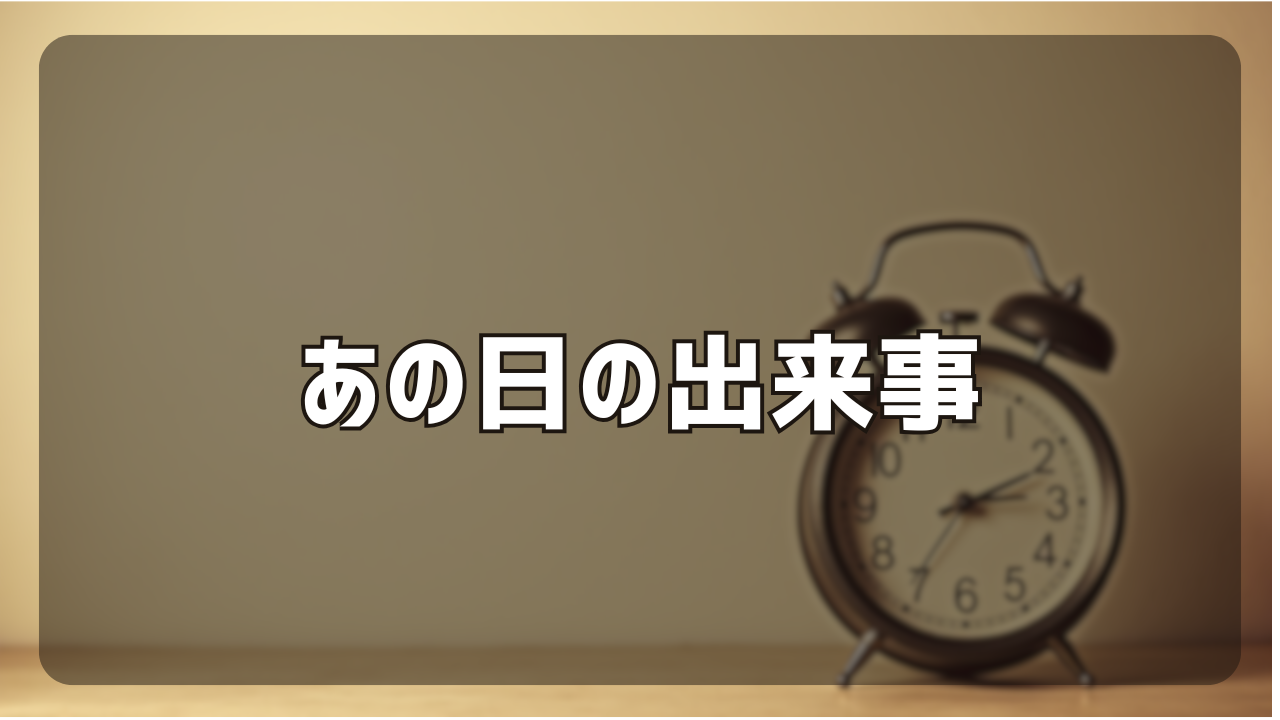


コメント