かつて「通勤・通学中にケータイでテレビを見る」なんて、当たり前の光景がありました。
ワンセグという機能です。
でも、「そういえば最近ワンセグって見ないよね…?」と感じる人も多いはず。
実際、スマートフォンからはほとんど姿を消してしまいました。
今回は、ワンセグの現在の状況と、その背景、そして今後どんな可能性があるのかをわかりやすく解説します。
そもそもワンセグって何だったの?
ワンセグとは、地上デジタル放送の一部(1セグメント)を使って、モバイル機器向けにテレビを配信する仕組みのこと。
2006年ごろから本格的にスタートし、当時のガラケーには当たり前のように搭載されていました。
ネット通信なしでテレビが見られるので、移動中の「ながら見」にピッタリなサービスでした。
なぜ消えた?ワンセグが見られなくなった理由
理由①:TVerなどの動画配信サービスの普及
「TVer」や「YouTube」など、好きな番組を好きな時間に見られるサービスが一般的に。
「リアルタイムでテレビを見る必要ある?」という価値観が広まりました。
理由②:通信環境の進化
今は5Gも普及し、スマホでサクサク高画質動画が見られます。
わざわざ画質の荒いワンセグに頼る必要がなくなったんです。
理由③:スマホの軽量化・スリム化
スマホを軽く、薄くするために、あまり使われない機能はどんどん削除される傾向に。
ワンセグ用のチューナーも、その対象になってしまいました。
理由④:そもそもテレビを見る人が減った
若い世代を中心に「テレビ離れ」が進んでいるのも要因です。
テレビを見ない人にとっては、ワンセグも必要ない機能でした。
実はまだ現役?ワンセグが残っている場所
シニア向けスマホやカーナビに搭載
シンプルで使いやすさ重視のシニア向けスマートフォンには、最近までワンセグ搭載モデルがありました。(価格ドットコム)
また、大半のカーナビでテレビ視聴が可能です。
災害時の「命綱」としての役割
災害でインターネットが使えなくなったとき、ワンセグはテレビ電波だけで情報を受信できるのが強みです。
最近は、ワンセグ付きの防災ラジオやポータブルテレビも販売されています。
手回し充電や乾電池で動くものもあり、災害対策グッズとして注目されています。
「地域ワンセグ」という新たな使い方も
一部地域では、地元のニュースや防災情報を発信する「地域ワンセグ」という仕組みもスタート。
まだ全国的に普及してはいませんが、ローカル密着型メディアとしての可能性が期待されています。(例:オワセグ)
それでも課題は多い
とはいえ、再び広く普及するにはいくつかの課題があります。
- 画質が低い
スマホやタブレットの高画質に比べると、ワンセグの映像はどうしても荒く感じます。 - 受信環境に左右される
場所によっては電波が入りにくく、映らないことも。 - NHK受信料の問題
「ワンセグ付き機器=テレビ」と見なされ、NHK受信料の対象になる可能性があります。
まとめ:ワンセグは「終わった技術」じゃないかも?
確かに、今のスマホからワンセグはほぼ姿を消しました。
ですが、災害対策ツールとしてのニーズや、地域限定の情報発信ツールとしての価値は、まだまだ残っています。
これからの社会やライフスタイルの変化次第で、“第二のワンセグブーム”が来るかもしれませんね。
あなたの家には、ワンセグ付きの機器がありますか?
万が一の災害に備えて、1台持っておくと安心かもしれません。
気になる方は、防災ラジオやポータブルテレビのチェックをしてみてはいかがでしょうか?
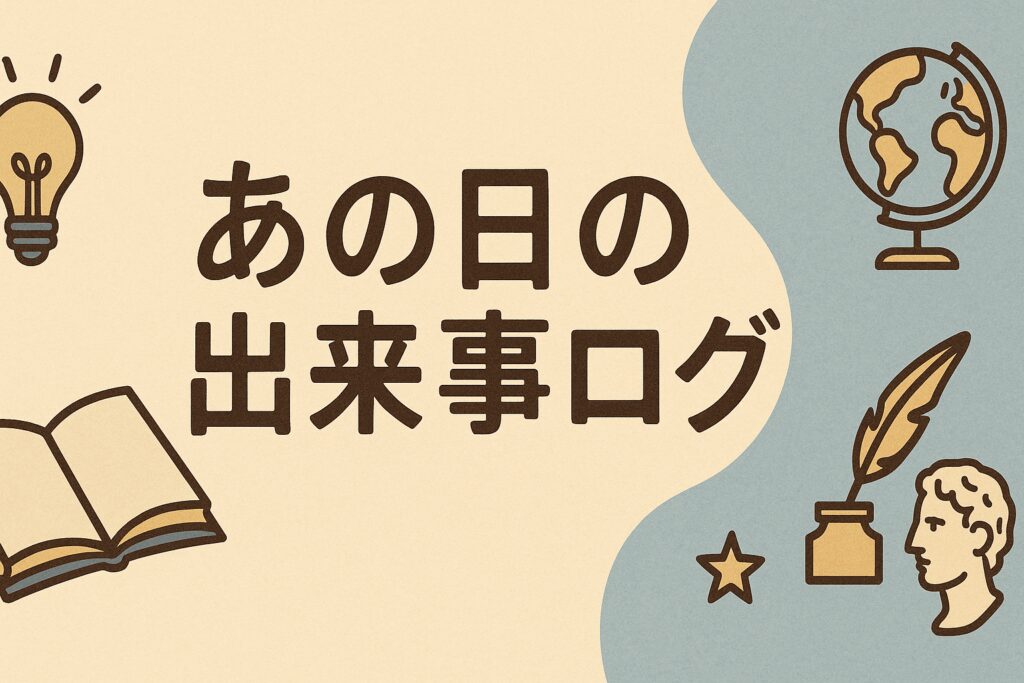

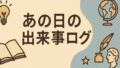
コメント