ゴールデンウィーク直前の4月28日も私たち日本人にとって非常に重要な意味を持つ日なんですよ。この日は「主権回復の日」。第二次世界大戦に敗れた日本が、再び独立国家として歩み始めた日です。
今日は、この「主権回復の日」が一体どういう日なのか、そしてこの出来事が現在の日本にどのように繋がっているのかを、特に日米関係と沖縄の状況に触れながら分かりやすくご紹介したいと思います。
7年間の占領が終わり、日本が独立を取り戻した日
第二次世界大戦で敗れた日本は、1945年から連合国軍の占領下に置かれました。国の政治や社会のあり方について、様々な制限があった時代です。
そんな占領期間が終わったのが、1952年4月28日。前年にアメリカのサンフランシスコで署名された「日本国との平和条約」、いわゆるサンフランシスコ平和条約がこの日に発効したからです。
この条約によって、日本は連合国との戦争状態を正式に終結させ、独立国家としての主権を取り戻しました。国際社会の一員として、自らの意思で物事を決め、国際的な取り決めにも参加できるようになり、その後の日本の経済成長や社会の発展の大きな一歩となりました。
主権回復と同時に結ばれた「旧」日米安全保障条約
サンフランシスコ平和条約が発効したのと同じ日、日本とアメリカの間で「日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約」(旧安保条約)が署名され、発効しました。
この旧安保条約は、当時の国際情勢、特に冷戦下において、十分な防衛力を持たない日本が自国の安全を確保するために、アメリカ軍の日本国内への駐留を認めるという性格が強いものでした。日本が米軍に基地を提供する一方、アメリカの日本を防衛する義務は明確には記されていませんでした。
「相互協力」へと変わった現在の安全保障条約
その後、日米を取り巻く状況の変化や、条約内容への様々な議論を経て、1960年に旧安保条約は改定され、「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約」(現行安保条約)となりました。
大きな違いは、条約名に「相互協力」という言葉が加わったことからもわかるように、アメリカの日本に対する防衛義務がより明確になり、日米が対等な立場で協力して安全保障に取り組むという相互協力の性格が強まった点です。これにより、日米同盟は日本の安全保障の基軸として位置づけられています。
主権回復、そして沖縄の復帰と基地問題
サンフランシスコ平和条約によって日本本土の主権は回復しましたが、沖縄(北緯29度以南の南西諸島)や小笠原諸島などはアメリカの施政権下に置かれることになりました。
※なお、奄美群島は1953年、小笠原諸島は1968年に日本へ返還されています。
沖縄では、長引くアメリカ施政下への不安や、広大な土地が米軍基地として利用されることへの反発から、日本への早期復帰を求める運動が高まりました。
その結果、サンフランシスコ平和条約発効から20年後の1972年5月15日、沖縄は正式に日本へ復帰しました。
しかし、沖縄復帰後も、在日米軍専用施設の約70%以上が沖縄県に集中している現状は変わっていません。
騒音、事件・事故、環境問題など、米軍基地をめぐる課題は今もなお続いており、日本全体の安全保障政策と沖縄の負担の関係性についての議論は続いています。
「主権回復の日」に、日本の過去・現在・未来を考える
4月28日の主権回復は、日本が独立国家として再出発するための重要な節目でした。しかし、その道のりは決して平坦ではなく、日米安全保障条約のあり方や、特に沖縄における基地問題など、現在まで続く様々な課題を残しています。
「主権回復の日」を迎えるにあたり、私たちは日本の独立がどのように達成されたのか、そしてそれが現在の安全保障や特定の地域にどのような影響を与えているのかを改めて考え、これらの課題にどう向き合っていくのかを考える機会とすることができるでしょう。
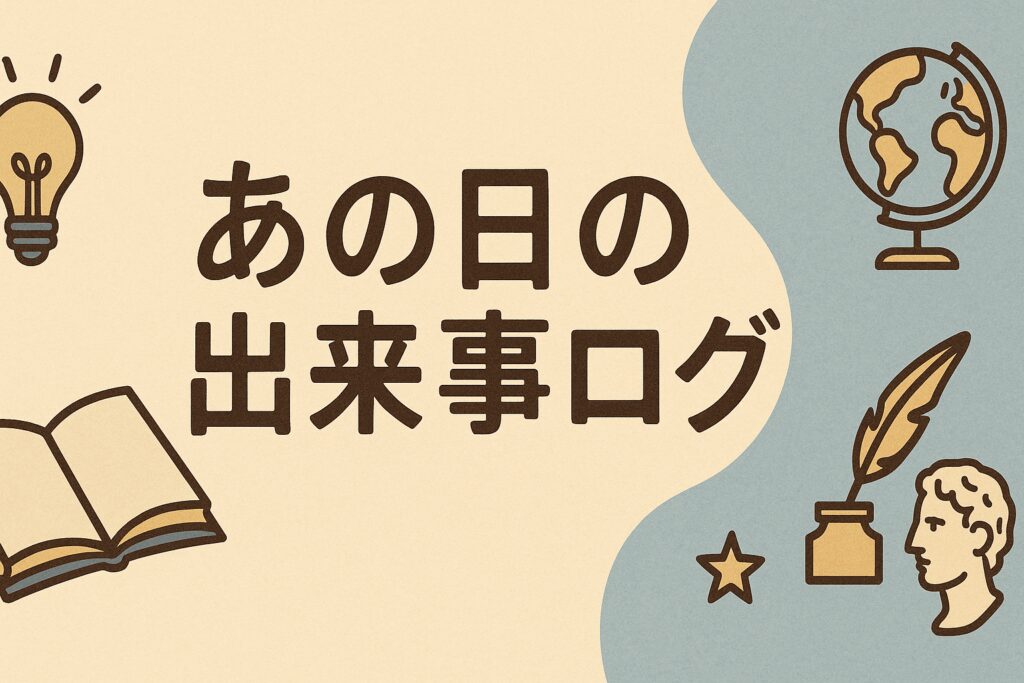

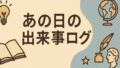
コメント