毎年、春になると心待ちにしている方も多いのではないでしょうか。4月末から5月にかけて続く大型連休、通称「ゴールデンウィーク」。旅行やレジャーなど、様々な計画を立てる楽しい期間ですが、そもそもなぜこの時期が連休になり、「ゴールデンウィーク」と呼ばれるようになったのか、その由来をご存じでしょうか。
この大型連休が生まれたきっかけは、1948年に施行された「国民の祝日に関する法律」です。これにより、4月29日の天皇誕生日(現在の昭和の日)、5月3日の憲法記念日、5月5日のこどもの日が祝日として定められました。
そして、「ゴールデンウィーク」という呼び名が誕生したのは、それからしばらく経った1950年代初頭のこと。この呼び名にはいくつかの説がありますが、有力とされているのは映画業界から生まれたという説です。
当時、5月の連休期間中は多くの人が休日を利用して映画館を訪れ、興行成績が非常に良かったそうです。そこで、映画会社が大勢のお客さんに来てもらうための宣伝として、この集客が見込める期間を「黄金週間」と名付けました。これがラジオの聴取率が高い時間帯を指す「ゴールデンタイム」に倣ったものだと言われています。その後、「黄金週間」という言葉が一般にも広まり、より覚えやすくインパクトのある「ゴールデンウィーク」というカタカナ表記が定着していったとされています。
また、連休中にラジオの聴取率が高かったことから、放送業界で「ゴールデンウィーク」と呼ばれるようになったという説もあります。どちらの説にしても、この期間が多くの人にとって特別な時期であり、注目度が高かったことが伺えます。
現在では、4月29日の昭和の日、5月3日の憲法記念日、5月4日のみどりの日、5月5日のこどもの日と祝日が続き、さらに間の平日が休みになることで、文字通りの大型連休となることが多いです。
このように、ゴールデンウィークは戦後の祝日制定と、当時の娯楽産業の盛り上がりの中で生まれた言葉です。由来を知ると、また違った視点でこの連休を楽しめるかもしれませんね。
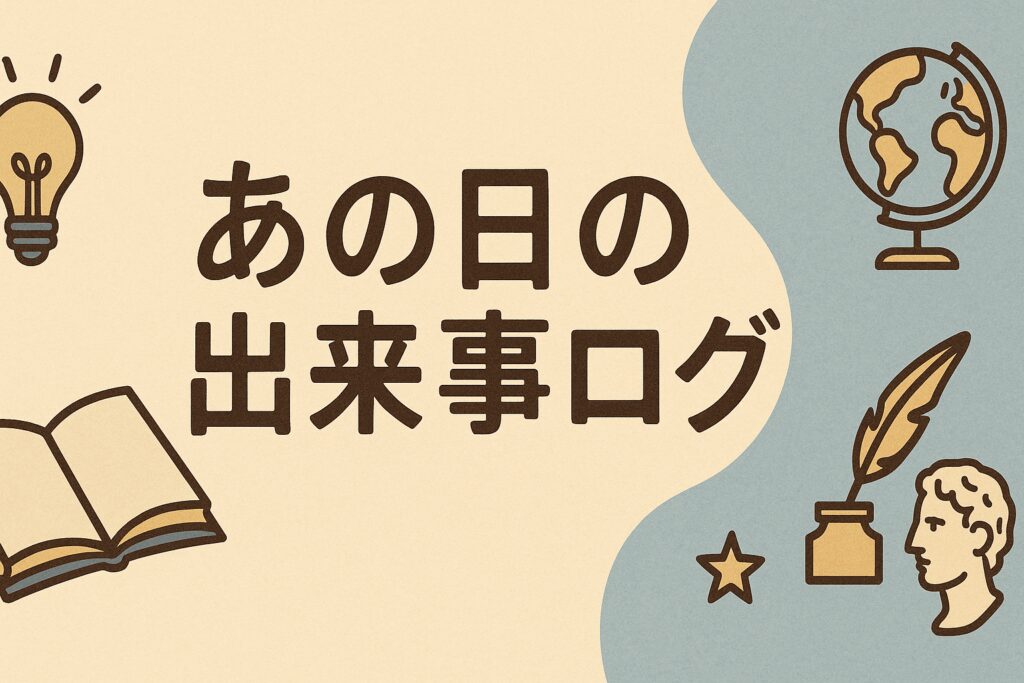
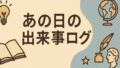

コメント