4月というと新年度の始まり。入学式や入社式、新しい部署でのスタートなど、フレッシュなイメージが強いですよね。でも、この「4月はじまり」という制度、実は海外と比べると少し珍しいって知っていましたか?
今日は、なぜ日本の年度が4月はじまりなのか、そして世界の他の国ではどうなっているのか、その違いがどんな影響をもたらすのかを分かりやすくお話ししたいと思います。
日本の4月はじまり、その理由をおさらい
なぜ日本の年度は4月からはじまるのでしょうか?これにはいくつかの歴史的な理由があります。
- 国の会計年度の影響: 明治19年(1886年)に国の会計年度が4月1日から翌年3月31日までと定められたことが、学校や企業の年度始まりに大きく関係しています。国からの予算で運営される学校などが、この会計年度に合わせた方が都合が良かったためです。
国の会計年度がなぜ4月始まりになったかについては諸説あります。明治時代に税収の柱であったお米の収穫時期との関連や、財政上の理由に加え当時経済的に先進的であったイギリスの会計年度を参考にしたことなどが挙げられています。 - 学校制度の歴史: 明治時代に近代的な学校制度が導入された当初は、欧米の制度を参考にしたこともあり、9月始まりが採用されていました。 しかし、国の会計年度が4月始まりに固定されると、学校運営の都合からそれに合わせる動きが広がりました。また一説には、農業社会との相性(秋の農繁期に学業どころではない)や、同時期に陸軍士官学校の入学時期が4月になったため、一般の学校も優秀な人材が先に軍に流れるのを避けるために4月始まりにした、という理由も挙げられています。このような背景から、9月始まりは断念され、 徐々に4月始まりへと移行し、定着していきました。
- 社会的な慣習: 会計年度や学校年度が4月始まりとなったことが、社会全体の慣習として根付き、多くの企業もこれに合わせて年度を設定するようになりました。春という季節も新しい始まりのイメージと重なり、自然に受け入れられていった面もあるでしょう。
世界の年度、いつから始まるのが一般的なの?
それでは、海外では年度がいつから始まるのでしょうか?日本のように4月はじまりの国もありますが、多くの国では異なる時期が一般的です。
- 学校年度: 世界で最も多いのは、夏の長期休暇が終わった後の9月に新学年が始まるパターンです。欧米の多くの国がこの制度を採用しています。南半球では季節が逆なので、1月や2月に新学年が始まるところが多いです。
・北半球(アメリカ・カナダ・ヨーロッパ)では、9月始まりが一般的です。
・南半球(オーストラリア・ニュージーランド・南アフリカなど)では、季節が逆なため1月 や2月始まりが多くなっています。 - 会計年度:国によってまちまちですが、
・アメリカ政府:10月始まり
・イギリス・インド:4月始まり
・ドイツ・フランス:1月始まり(暦年と同じ)
つまり、世界の多くの地域では「9月入学・9月始まり」、または「1月入学・1月始まり」が多く、日本の「4月入学・4月始まり」は、決して世界の多数派ではないのです。
年度始まりの違いがもたらす「ズレ」
日本と海外で年度始まりが違うことは、グローバル化が進んだ現代において、いくつかの「ズレ」を生じさせることがあります。
- 留学や海外との学生交流: 日本の学校年度と海外の学校年度がずれているため、日本の学生が海外に留学したり、海外から学生を受け入れたりする際に、学年や学期の区切りが合わず、調整が必要になることがあります。
- ビジネスシーン: 海外の企業と取引をする際に、相手の会計年度と日本の会計年度が違うと、決算期や予算のタイミングが合わないことがあります。
- 社会的な区切り: 入学や卒業、就職といった人生の大きな区切りが訪れる時期が異なるため、国際的な感覚に違いが生まれることがあります。
まとめ:違いを知り、向き合う
日本の年度が4月はじまりなのは、国の歴史や制度の中で形成されてきた独自の文化とも言えます。明治時代には一度9月始まりが採用されながらも、様々な理由から現在の4月始まりに落ち着きました。一方、世界の多くの国が異なる時期を年度の始まりとしているのには、それぞれの国の背景があります。
グローバルな繋がりがますます深まる中で、この年度始まりの違いを理解することは、海外の人々とのコミュニケーションや、国際的な活動を行う上で大切なことと言えるでしょう。そして、国際標準とのずれをどう捉え、今後の日本の制度をどうしていくのか、議論は続いています。
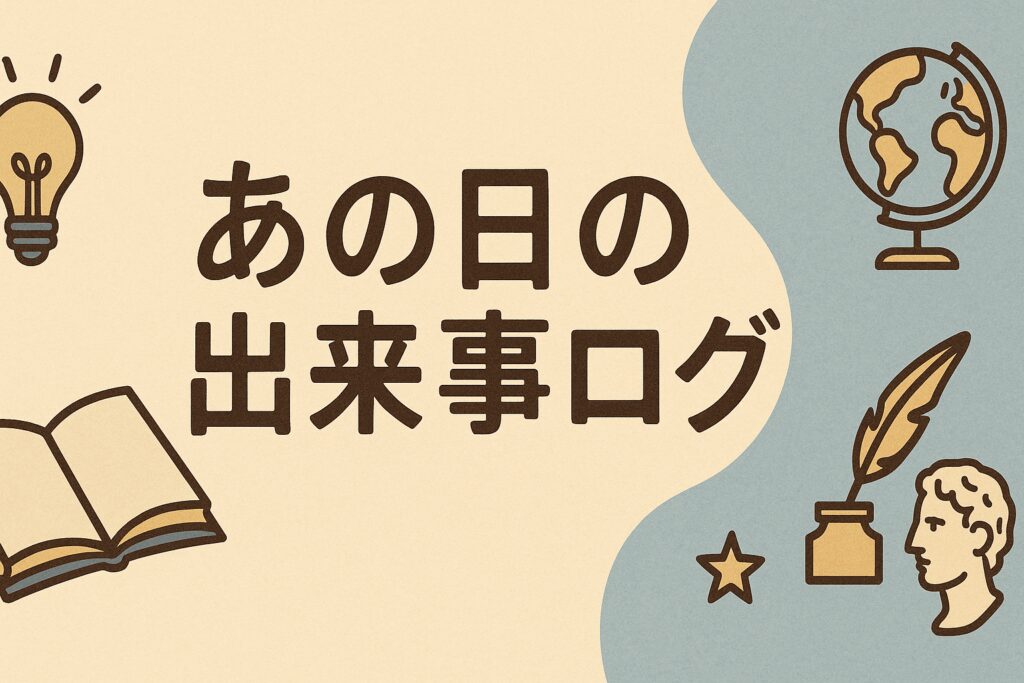
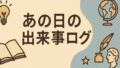

コメント