1902年(明治35年)1月、青森県の八甲田山で発生した「八甲田雪中行軍遭難事件」。これは、日本陸軍の冬季訓練中に起こった史上最悪の山岳遭難事故であり、210名中199名が命を落とすという、痛ましい結末を迎えました。
極寒の雪山で起きたこの悲劇は、単なる自然災害ではなく、軍組織の構造的欠陥と判断ミスが引き起こした“人災”として、今もなお語り継がれています。
日露戦争前夜──なぜ「雪中行軍」は行われたのか?
明治後期、日本は急速な近代化と軍備増強を進める中で、ロシアとの緊張が高まりつつありました。特に、朝鮮半島や満州をめぐる利権争いは激化し、開戦は時間の問題と見られていました。
そうした情勢を受け、陸軍内部では「極寒地での行軍能力を高める必要性」が叫ばれます。ロシアのような寒冷地での作戦行動を想定し、雪山を徒歩で踏破する訓練、いわゆる「寒地行軍」が計画されました。これが、のちに惨事へとつながる「八甲田雪中行軍訓練」の発端でした。
二つのルート、対照的な運命
訓練には2つの部隊が参加していました。
- 弘前歩兵第31連隊:弘前〜青森間の比較的平坦な往復ルートを担当
- 青森歩兵第5連隊:青森から八甲田山を越えて田代新湯(現・十和田市)を目指す高難易度ルートを担当
このうち、青森第5連隊の選んだルートは、標高差が大きく、厳しい気象条件が重なる「冬山登山の難所」として知られていました。当時から「自殺行軍」とまで揶揄されたほど過酷な道でしたが、なぜこのルートを選んだのかは今なお議論が分かれています。
運命の日──1902年1月23日、行軍開始
1902年1月23日、青森第5連隊の210名は早朝に青森を出発し、目的地・田代新湯へ向けて行軍を開始しました。しかし間もなく、猛烈な吹雪が部隊を襲います。視界はほぼゼロ、気温は氷点下20℃以下。
この極限の状況下、隊列は乱れ、方向感覚を失った兵士たちは雪山をさまようことになります。
当時の軍装は現在のような防寒装備とは程遠く、兵士たちは薄手の軍服にわずかな携行食糧しか持っていませんでした。無謀とも言える条件下での行軍は、まさに「死の行進」でした。
雪の地獄で何が起きたのか
激しい吹雪と凍てつく寒さにより、兵士たちは次々と力尽き倒れていきます。低体温症により錯乱し、衣服を脱ぎ捨てる「矛盾脱衣(パラドキシカル・アンディスロービング)」と呼ばれる行動を取る者もいました。仲間の亡骸に寄り添ったまま凍死した兵士もいたと記録されています。
指揮官・神成大尉は途中で消息を絶ち、指揮系統は完全に崩壊。部隊は無秩序な状態となり、多くの兵士が助けも得られないまま雪山で命を落としました。
奇跡の生還──後藤伍長のエピソード
210名のうち、奇跡的に救出されたのは17名。しかし、そのうち6名は治療の甲斐なく死亡し、最終的な生存者はわずか11名でした。
その中のひとり、後藤房之助伍長は数日間にわたり雪中をさまよい続け、救助隊が発見した時には『仮死状態で歩哨の如く立っていた』と伝えられています。この逸話は事件の象徴となり、彼を模した銅像は現在も八甲田山に建てられています。

CC 表示-継承 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=29355
なぜここまでの大惨事になったのか?
この悲劇には、複数の要因が複雑に絡み合っていました。
1. 気象情報の軽視
出発前から天候悪化の兆候があったにもかかわらず、「予定通り実施すべし」という軍の方針が優先されました。
2. 装備・知識の不足
防寒具や携帯食糧、雪山での移動ノウハウも不十分で、凍傷や低体温症への備えは皆無に近い状態でした。
3. 指揮と判断の欠如
現場での柔軟な判断力や連携体制が機能せず、隊員の安全より「計画遂行」が重視されたことで、犠牲が拡大しました。
指揮官の責任と軍の構造的問題
この訓練を主導したのは、青森歩兵第5連隊長・津川義三中佐。彼は寒地訓練の重要性を強く訴えた人物でしたが、自らは行軍には同行せず、後方からの指示にとどまりました。
天候の変化や装備に対する認識が甘く、「成功ありき」の組織文化も災いしました。訓練の中止や延期の選択肢が排除されていた点は、組織的な問題として指摘されています。
津川中佐は軍法会議にはかけられなかったものの、事件後は中央から外され、事実上の更迭となりました。
八甲田雪中行軍を題材とした作品と教訓
この事件は、のちに小説『八甲田山死の彷徨』(新田次郎)、映画『八甲田山』(1977年)などの作品の題材となり、広く知られるようになりました。
高倉健らが出演した映画では、過酷なロケーション撮影とリアリズム重視の演出が話題を呼びました。「天は我々を見放した」は当時の流行語になり、配給収入の25億900万円は1977年の日本映画第1位を記録しました。
現在、八甲田山には慰霊碑が建てられ、自衛隊は寒冷地訓練における装備や安全対策を徹底しています。防災教育や危機管理の教材としても活用されており、100年以上たった今もなお、事件は教訓として生き続けています。
まとめ:「想定外」をなくすために──自然とどう向き合うか
1902年当時、気象予測技術は未熟であり、衛星や数値予報は存在しませんでした。現代ではスマートフォンで天気を確認し、GPSや通信機器で位置情報を共有できます。しかし、最も重要なのは「過信しない姿勢」です。
「想定外だった」では済まされない。
自然に対する謙虚な姿勢と、冷静なリスク評価こそが、私たちが次の災害を防ぐために持つべき教訓なのです。
「八甲田雪中行軍遭難事件」は、自然の脅威と人間の過信が引き起こした、まさに“人災”とも言える悲劇です。勇敢さと無謀さは紙一重。自然を相手にする以上、人間は常に謙虚であるべき──。この事件は100年以上経った今も、私たちにそう語りかけています。
※本記事は、Wikipedia「八甲田雪中行軍遭難事件」を参考にし、CC BY-SA 4.0ライセンスのもとで要約・再構成しています。
オリジナルの全文はWikipediaにてご確認いただけます。
著作権およびライセンスについてはクリエイティブ・コモンズ 表示-継承ライセンスに準拠しています。
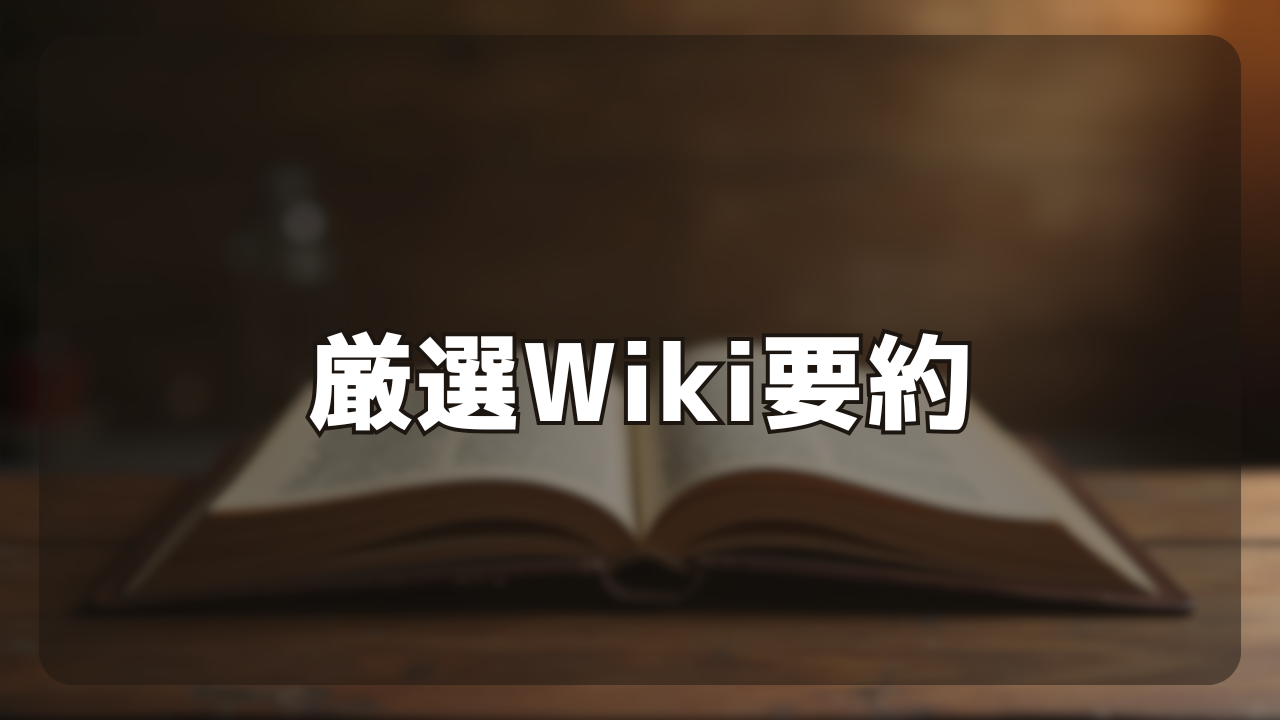
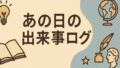

コメント