「風林火山(ふうりんかざん)」。
武田信玄の軍旗に掲げられたこの四文字は、日本人なら誰もが知る戦略の代名詞です。
疾(はや)きこと風の如く、
徐(しず)かなること林の如く、
侵(おか)すこと火の如く、
動かざること山の如し。
スピード・冷静さ・攻撃力・安定感。
まさに戦国武将の理想像を凝縮したような言葉ですが、実はこの「風林火山」はここで終わりではありません。
原典である『孫子の兵法・軍争篇』には、このあとにさらに続きがあるのです。
「風林火山」の原文と、その“続き”
『孫子』軍争篇の該当部分をすべて抜き出すと、こうなります。
其疾如風、其徐如林、侵掠如火、不動如山、
難知如陰、動如雷霆、掠郷分衆、廓地分利、懸權而動。
つまり、「風林火山」に続くのは次の五句。
- 難知如陰(なんち いんに ごとく)
- 動如雷霆(どう らいていに ごとし)
- 掠郷分衆(りゃくきょう しゅうをわかつ)
- 廓地分利(かくち りをわかつ)
- 懸權而動(けんけん して うごく)
この九句で、孫子は「軍の理想的な在り方」を体系的に示しています。
では、それぞれの意味を見ていきましょう。
難知如陰 — 「知り難きこと陰の如く」
陰(かげ)のように、相手に意図を悟らせるな。
つまり、戦略は表に出すなという教えです。
情報戦の重要性を、すでに2500年前に見抜いていたのです。
動如雷霆 — 「動くこと雷霆の如し」
雷霆とは雷鳴と稲妻。
一度動けば、雷のように激しく、敵に反応させる間を与えない。
「難知如陰」と対になる、静から動への瞬発力を説いています。
掠郷分衆 — 「郷を掠(かす)めて衆を分かつ」
これは「敵地を略奪したら、戦利品を兵に平等に分けよ」という意。
つまり、兵の士気を維持する公平な報酬分配を説いています。
単なる略奪ではなく、秩序ある管理の重要性を強調しています。
廓地分利 — 「地を廓(ひら)いて利を分かつ」
「廓地」とは、占領した土地を整備し、有利な位置を確保すること。
単に攻め落とすだけでなく、地形・補給・利権を戦略的に管理せよという意味です。
現代でいえば「戦後の持続可能な支配」を見据えた戦略。
懸權而動 — 「権を懸(か)けて而して動く。」
「懸權」とは、状況に応じて秤を動かすように判断すること。
つまり、戦機を計って動けという教えです。
勢いだけで突撃するのではなく、常に「動くべき時か否か」を天秤にかけよ——。
孫子が最も重視する「状況判断と柔軟性」を象徴する句です。
「風林火山」だけを掲げた理由
武田信玄が『孫子の兵法』を深く研究していたことは、複数の史料からも確認されています。
彼は若い頃から中国古典、とくに兵法書を愛読し、「孫子を以て師とす」とまで語ったと伝わります。
実際、信玄の戦術には「地形の利用」「兵の分散と集中」「戦わずして勝つ」といった孫子の思想が色濃く反映されており、単なる引用ではなく実戦に応用した知的戦略家でした。
それだけに、信玄が「風林火山」の出典を知らなかったということは考えにくい。
むしろ彼は『孫子』の続き――「難知如陰」「動如雷霆」「掠郷分衆」「廓地分利」「懸權而動」までをすべて理解したうえで、あえて旗印には掲げなかったと見るのが自然です。
つまり信玄は、“省略”ではなく“選択”を行ったのです。
この「選択」こそ、信玄の軍略と統治思想の核心に触れる部分でもあります。
では、なぜ彼は後半の五句を掲げなかったのか
軍旗としての実用性と「象徴」の力
軍旗は戦場で一目で認識され、士気を高め、部隊の規律を示す道具です。長文を掲げるより、短く視覚的に強い言葉を選ぶのが効果的。4語の凝縮されたリズムは、遠くからでも読みやすく覚えやすいため、信玄が「孫子四如(しじょ)」として四句を抜き出したのは、旗というメディアの制約と「象徴としての美しさ」を優先した結果と考えられます。
「後半句」は外に掲げるにはセンシティブな内容を含む
『孫子』の続き(難知如陰・動如雷霆・掠郷分衆・廓地分利・懸權而動)は、敵を欺くこと、略奪の分配、地利の管理、状況に合わせた権衡の使用など、実務的かつ政治的な含みを持ちます。これらを公然と旗に掲げれば、対外的には「欺瞞や略奪を肯定する軍だ」と受け取られる恐れがあるため、信玄はあえて「美しく規範的に見える部分」だけを抜粋した――という合理的な読みが成り立ちます。
士気・統率・内向けメッセージとしての機能
旗印は外向きの宣言であると同時に、内部統率のための合図でもあります。信玄は政治・内政にも才覚があり、軍の統率や家中の規律を重視していました。前半4句は「速やかに・慎重に・激しく・泰然と」といった行動規範を端的に示し、将兵が現場で即応できる“行動の基準”として機能します。複雑な後半句は主に作戦・統治の現場で口頭や秘策として運用すれば足り、旗はあくまで簡潔な行動指針に留めた、という見方です。
現代に通じる「九つの教え」
これを現代社会に置き換えると、驚くほど通じます。
| 孫子の句 | 現代的意味 |
|---|---|
| 疾如風 | チャンスを逃さぬスピード感 |
| 徐如林 | チームワークと安定 |
| 侵掠如火 | 攻め時には情熱を燃やす |
| 不動如山 | 信念と持続力 |
| 難知如陰 | 情報はむやみに漏らさない |
| 動如雷霆 | 決断したら即行動 |
| 掠郷分衆 | 成果はチームで分かち合う |
| 廓地分利 | 環境とリソースを整備する |
| 懸權而動 | 状況を見極め、タイミングを計る |
2500年前の軍略が、今なおビジネスや人間関係の原理に通じている——。
まさに「孫子の兵法」が古びない理由が、ここにあります。
まとめ
疾きこと風の如く、
徐かなること林の如く、
侵すこと火の如く、
動かざること山の如し、
知り難きこと陰の如く、
動くこと雷霆の如し、
郷を掠(かす)めて衆を分かち、
地を廊(ひろ)めて利を分かち、
権を懸けて而して動く。
この九句が、孫子が語った「戦を制する者」の全体像。
信玄の旗印は、その中でも最も象徴的で美しい“前半”を掲げたにすぎません。
「風林火山の“その先”」にあるのは、スピードや力ではなく、判断と統制の知恵。
そこにこそ、時代を超えて受け継がれる“戦略の本質”が隠されているのです。


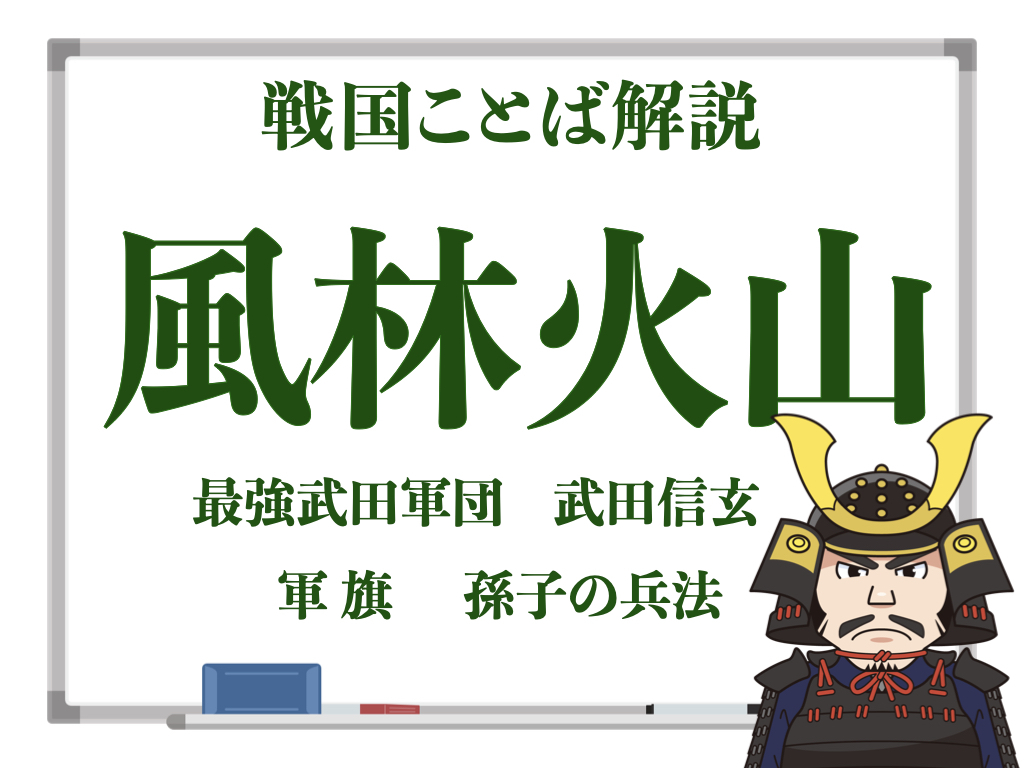


コメント