1959年2月、旧ソビエト連邦のウラル山脈で、9人の若者が不可解な死を遂げる事件が発生しました。彼らは全員が登山経験のある学生で、目的地のオトルテン山に向かう道中で行方不明になります。
この事件は、発見された遺体の状況や不可解な証拠から、60年以上経った今も「未解決事件」として世界中の関心を集め続けています。
事件発生まで
1959年、ウラル工科大学(当時:ウラル科学技術学校)の学生・卒業生9名(男性7名・女性2名)と1名の途中離脱者を含む計10名の登山グループが、スキーによる山岳トレッキングを計画。
- イーゴリ・アレクセーエヴィチ・ディアトロフ 、一行のリーダー
- ジナイダ・アレクセーエヴナ・コルモゴロワ
- リュドミラ・アレクサンドロヴナ・ドゥビニナ
- アレクサンドル・セルゲーエヴィチ・コレヴァトフ
- ルステム・ウラジーミロヴィチ・スロボディン
- ユーリー(ゲオルギー)・アレクセーエヴィチ・クリヴォニシチェンコ
- ユーリー・ニコラエヴィチ・ドロシェンコ
- ニコライ・ウラジーミロヴィチ・チボ=ブリニョーリ
- セミョーン(アレクサンドル)・アレクサンドロヴィチ・ゾロタリョフ
- ユーリー・エフィモヴィチ・ユーディン
目的地はウラル山脈北部のオトルテン山で、トレッキング第3級の資格取得のために難易度の高いルートが選ばれました。
1月25日にスヴェルドロフスク州北部の中心地イヴデルに到着後、彼らは最終有人集落ヴィジャイ、伐採者の居住地「第41区」を経て、1月27日にオトルテン山へ向け出発。翌日、持病のリウマチの悪化によりユーリー・ユーディン10が離脱し、グループは9名となりました。
1月31日にはオトルテン山麓に到達し、下山までに必要な食料の取り分けや帰路に備えた余剰物資の残置などを準備を整え、本格的な登山を開始します。
2月1日、一行は悪天候により方向を見失い、道を逸れてオトルテン山の南側にあるホラート・シャフイル山(ホラチャフリ)の斜面に誤って入り込みます。
彼らはそこから引き返すことなくキャンプを設営しましたが、その後行方不明となってしまいます。
捜索と発見
捜索要請
登山グループは2月12日にヴィジャイに戻る予定でしたが、リーダーのディアトロフ1が事前に「遠征が長引くかもしれない」と話していたため、期日を過ぎてもすぐには騒がれませんでした。
2月20日になってようやく、一行の親族たちの要請でウラル科学技術学校が捜索隊を組織し、航空機による捜索が始まりました。同日にイヴデリ検察局も事件性を考慮し刑事捜査を開始します。
2月22日に大学から追加の捜索隊が派遣され、以降ボランティアも加わり地上と空から捜索が行われました。
テントの発見
2月26日、捜索隊はホラート・シャフイル山で、損傷したテントを発見しました。テントは雪に埋もれており、内側から切り裂かれていたことが判明しました。
テント内には荷物が残されており、そこから9人分の足跡が渓谷方向へ続いていましたが、途中で雪に覆われて消えていました。
最初の遺体の発見
捜索隊は、大きなヒマラヤスギの木の下で焚き火の跡を発見し、その近くでユーリー・クリヴォニシェンコ6とユーリー・ドロシェンコ7の遺体を発見しました。2人とも下着姿で靴も履いていませんでした。木の枝が5メートルの高さまで折れていたことから、誰かが木に登って周囲を確認しようとした可能性がありました。
その後、同じ木とテントの間で、ディアトロフ1、ジナイダ・コルモゴロワ2、ルステム・スロボディン5の3名の遺体も見つかりました。彼らの遺体はそれぞれテントに向かって移動する方向で倒れており、キャンプに戻ろうとしていたと推察されています。
残りの遺体の発見
残る4名の遺体は約2か月後の5月4日に、森の奥の渓谷で発見されました。彼らは4メートルの積雪の下に埋もれており、比較的しっかりとした服装をしていました。
これは、先に亡くなった仲間の衣類を着用していたと推察されています。例えば、ゾロタリョフ9はドゥビニナ3のコートと帽子を身につけており、ドゥビニナ3の足にはクリヴォニシェンコ6のズボンの一部が巻かれていました。
検死結果から浮かび上がった謎
検死結果と不自然な損傷
最初に見つかった5人の遺体は3月に検死され、スロボディン5は頭蓋骨に小さな亀裂を負っていたものの、いずれも死因は低体温症で致命傷は確認されませんでした。
後に発見された遺体と異常な損傷
5月に発見された残り4人の遺体のうち3人には深刻な損傷が見られました。
チボ=ブリニョール8は頭部に重傷を負っており、これが致命傷とされました。
ドゥビニナ3とゾロタリョフ9の胸部は重度の骨折をしていました。この損傷は、交通事故に匹敵するほどの強い力によるものでしたが、骨折に伴う外傷がないことから高圧力によるものと推察されました。
また、ドゥビニナ3は舌、目、唇の一部、顔面組織、頭蓋骨の一部、ゾロタリョフ9は眼球、コレヴァトフ4は眉毛を失っていました。
低体温症と「矛盾脱衣」
マイナス30度の極寒の中、遺体の多くは薄着で、靴を履いていない者もいました。これは「矛盾脱衣」と呼ばれる低体温症の症状のひとつで、極度の寒さによる混乱状態で服を脱いでしまう現象と考えられています。一部の者は、すでに亡くなった仲間の衣類を切って巻きつけていた形跡も見られました。
検死結果のまとめ
| 番号 | 名前 | 性別 | 死因 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | イーゴリ・アレクセーエヴィチ・ディアトロフ | 男 | 低体温症 | リーダー |
| 2 | ジナイダ・アレクセーエヴナ・コルモゴロワ | 女 | 低体温症 | |
| 3 | リュドミラ・アレクサンドロヴナ・ドゥビニナ | 女 | 重度の胸部損傷 | 顔面が最も損傷 |
| 4 | アレクサンドル・セルゲーエヴィチ・コレヴァトフ | 男 | 低体温症 | 眉毛の喪失 |
| 5 | ルステム・ウラジーミロヴィチ・スロボディン | 男 | 低体温症 | |
| 6 | ユーリー(ゲオルギー)・アレクセーエヴィチ・クリヴォニシチェンコ | 男 | 低体温症 | |
| 7 | ユーリー・ニコラエヴィチ・ドロシェンコ | 男 | 低体温症 | |
| 8 | ニコライ・ウラジーミロヴィチ・チボ=ブリニョーリ | 男 | 致命的な頭蓋骨損傷 | 激しい頭部の損傷 |
| 9 | セミョーン(アレクサンドル)・アレクサンドロヴィチ・ゾロタリョフ | 男 | 重度の胸部損傷 | 年長者(38歳) 眼球の喪失 |
| 10 | ユーリー・エフィモヴィチ・ユーディン | 男 | 遠征を途中で離脱 |
結果として、6人は低体温症による死亡と判断されましたが、残る3人には交通事故レベルの致命傷や不可解な損傷が確認され、自然災害や単なる事故では説明のつかない、謎に満ちた事件として今日まで議論が続いています。
事件の捜査と強引な幕引き
救助隊が発見したテントは内側から切り裂かれていました。テントは放棄されており、一行は靴下や裸足のまま“何か”から逃げ出していたとされています。
当初は先住民のマンシ人が、彼らの土地に侵入した一行を襲撃して殺害したのではないかとする憶測も流れましたが、現場に一行の足跡しか残っておらず、至近距離で争った形跡がないという状況から、この説は否定されました。
雪崩説とその限界
事件の原因として有力とされた説のひとつが「雪崩説」です。テントを押し潰した雪によってパニックが起き、一行は急いで避難したことで衣服を失い低体温症で亡くなったというシナリオです。
後で見つかった4人は助けを求めて渓谷に滑落し、3人がひどい骨折を負ったのもこのためと推察されました。
しかし、現地の傾斜が緩やかで雪崩の可能性が低いことや、足跡が残っていたことなどから、この説には否定的な見解もあります。
調査結果の不可解な点
事件には不可解な点が多く、何人かの衣類からは高い線量の放射線が検出されました。また、外傷がないにも関わらず致命傷を負っていた者がいたこと、眼球や舌が失われていたことも謎とされています。
- 6人は低体温症で死亡し、3人は致命的な怪我を負って死亡した。
- 9人以外にほかの者がいた様子も、その周辺地域に誰かがいた様子もなかった。
- テントは内側から切り開かれていた。
- 一行は最後に食事を摂ってから6~8時間後に死亡した。
- メンバー全員が自発的に歩いてキャンプ地を離れたことが判明した。
- 検死医は3人の遺体の致命傷は人間によるものではあり得ないと述べた。
- 何人かの犠牲者の衣服に、高い線量の放射能汚染が認められた。
- 発表された資料には、メンバーの内臓器官の状態に関する情報が含まれていなかった。
捜査の結論と資料の扱い
ソ連当局は、最終的に事件の原因を「抗いがたい自然の力」によるものと結論づけ、1959年5月に捜査は公式に終了し「犯人はいない」とされました。
ただし、その後長らく資料は機密扱いとされ、1990年代になってようやく一部が公開されましたが、いくつかの資料は失われたままとなっています。
事件をめぐる議論
捜査当局の見落としと指摘される点
一部の研究者たちは、捜査当局が重要な事実を見落とした、または意図的に無視したと主張しています。
- のちにディアトロフ財団の理事長となったユーリー・クンツェヴィチ氏は、犠牲者たちの葬儀に出席した際、肌が「濃い茶褐色」だったと証言しています。
- 数名のメンバーの衣類(ズボン2着とセーター)からは、高い線量の放射能が検出されました。
- 事件当夜、事件現場から南に約50キロ離れた場所にいた別の登山グループが、北の夜空にオレンジ色の光球を目撃しています。
軍事利用と隠蔽の可能性
- 現場付近には大量の金属くずが残されていたとされており、軍がこの地域を秘密裏に使用していた可能性が指摘されています。
- 最終キャンプ地は、バイコヌール宇宙基地とノヴァヤゼムリャ核実験場を結ぶルート上にあり、戦略的な位置であったことがうかがえます。
カメラの謎と「光体」
- テント内から回収されたカメラには、多くの写真が収められていました。その中の最後の1枚には、正体不明の「光体」が写っていたとされています。
音響現象によるパニック説
- アメリカ海洋大気庁のベダード博士は、現場の地形がカルマン渦(ヘアピン渦)という音響現象を引き起こしやすいことを指摘しています。この現象による轟音や超低周波音が、隊員たちをパニックに陥れ、キャンプを飛び出させた可能性があるとしています。
- この説はドキュメンタリー監督ドニー・アイカー氏によって『死に山』という著作で紹介されています。
放射線と遺体の損傷に関する解釈
- 眼球や舌の欠損は、野生動物による食害や水による腐敗が原因である可能性が高いと推測されています。
- 放射線レベルについてアイカー氏は、通常の2倍程度であれば北方の核実験場の影響でも説明が可能と述べています。
- 肌の変色(茶褐色)についても、雪原での長時間の日光曝露による日焼けと考えられます。
その後の動向
事件があった峠は一行のリーダーであったイーゴリ・ディアトロフの名前から、ディアトロフ峠と呼ばれるようになりました。
小説による事件の描写(1967年)
1967年、スヴェルドロフスク州の作家ユーリー・ヤロヴォイ氏が、小説『最高次の複雑性』を出版しました。この小説はディアトロフ事件に着想を得て執筆されたもので、彼自身も事件の捜索や初期調査にカメラマンとして関与していました。
ソ連時代の検閲の影響を受け、事件の美化や、登場人物の死が一部にとどめられるなど、内容は限定的でした。ヤロヴォイ氏が遺した資料や写真は、1980年の死後にすべて失われてしまいました。
情報公開と再調査の動き(1990年代)
1990年になると、事件の詳細が出版物や地元メディアを通じて公にされ始めました。アナトリー・グシチン氏は、死因審問の公式資料をもとに著作を執筆しましたが、一部の資料が意図的に削除されていたことを指摘しました。彼の著書『国家機密の価値は、9人の生命』は、軍の秘密兵器実験説を強調しすぎとの批判もありましたが、事件に対する関心を高めました。
また、元捜査官のレフ・イヴァノフ氏は1990年に、自身の著書で、捜査中に上層部から飛行体に関する情報を機密扱いにするよう指示されたと証言しています。彼は、UFOなどの超常現象が事件の背景にある可能性を信じていると述べています。
ドキュメンタリーとフィクションの融合(2000年以降)
2000年には地元テレビ局がドキュメンタリー番組『ディアトロフ峠の謎』を制作しました。この番組では、作家アンナ・マトヴェーエワ氏の協力のもと、事件を題材にしたフィクション小説が紹介されました。彼女の小説は、資料・証言・日記などをもとに構成されており、公表された資料の中でも特に充実した情報源として評価されています。
さらに、事件の資料や関連文書のコピーがWebフォーラムなどで徐々に公開され、研究者や一般市民の関心が高まりました。
ディアトロフ財団の設立と活動
エカテリンブルクでは、ユーリー・クンツェヴィチ氏によってディアトロフ財団が設立されました。ウラル工科大学の支援を受け、事件の再調査の要請と、犠牲者の記憶をとどめる記念館の運営が主な目的とされています。
ロシア検察による再調査(2018年~2020年)
2018年、遺族の要請を受けてロシア検察が事件の再調査を開始しました。
2020年7月、検察は「死亡原因は雪崩である」との公式見解を発表しました。しかし、遺族らで結成された民間団体はこの結論に納得せず、人為的な要因があったと主張し反論しています。
科学的シミュレーションによる雪崩説の裏付け(2021年)
2021年1月、スイスの研究者アレクサンダー・プズリン氏とヨハン・ガウメ氏が、表層雪崩による事故説を発表しました。
この研究には、映画『アナと雪の女王』で使われたCG技術や、1970年代の自動車用シートベルト研究の知見が活用されました。彼らは、わずか幅5メートルの雪崩でも致命的な被害を与える可能性があると主張しています。
また、衣類の放射線汚染はランタン用のトリウムによるもの、眼球や舌の損傷は野生動物による食害である可能性が高いとしています。
まとめ:自然か、それとも…?
捜査当局は事故として事件を終結させましたが、不可解な点が数多く残されており、真相はいまだ闇の中です。
これは単なる遭難事故だったのか。それとも、外部からの何らかの力が働いていたのか――。
いずれにせよ、彼らが最後に何を見て、何を恐れ、何を選んだのかを知るすべはもはやありません。
極寒の中でのキャンプ地放棄、不可解な遺体、そして捜査当局の一方的な結論……。
この事件の謎が、いつか解き明かされる日は訪れるのでしょうか。
自然現象だけでは説明しきれない、何か「異常な状況」が現場にあったのではないかと感じてしまいます。だからこそ、多くの人の関心を惹きつけてやまないのでしょう。
参考リンク
ディアトロフ峠事件:https://w.wiki/43m5
※本記事は、Wikipediaを参考にし、CC BY-SA 4.0ライセンスのもとで要約・再構成しています。
オリジナルの全文はWikipediaの該当ページにてご確認いただけます。
著作権およびライセンスについてはクリエイティブ・コモンズ 表示-継承ライセンスに準拠しています。
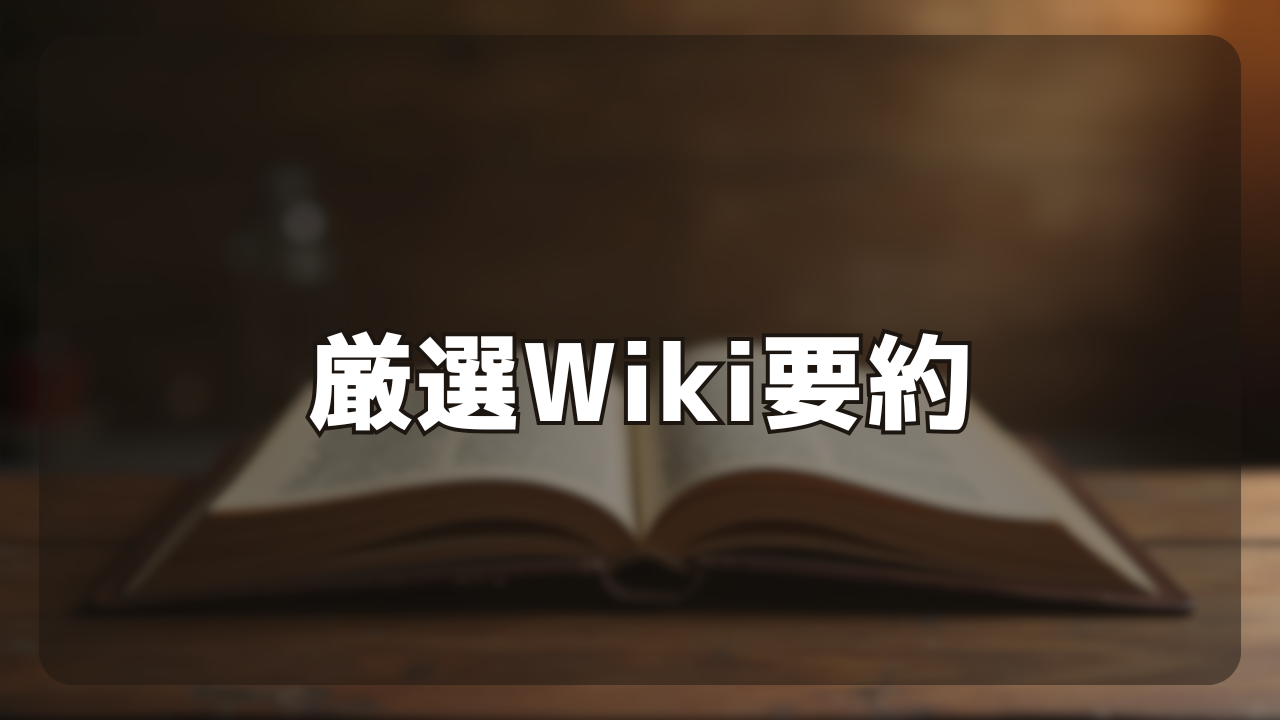
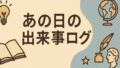

コメント