この記事は「地方病」シリーズの第3回です。過去の記事は以下のカードからご覧いただけます。
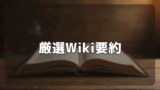
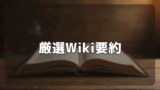
甲府盆地で行われた対策
日本住血吸虫の中間宿主がミヤイリガイであることが解明されたことで、その生息地が地方病(日本住血吸虫症)の流行地、すなわち有病地と重なることが明らかになりました。
大正末期から昭和初期にかけては、1平方メートルあたり100匹以上のミヤイリガイが確認される地域もありました。中には炊事場の窓枠にまで這い上がるほど密集する、異常な光景も見られたといいます。水陸両生の性質をもつミヤイリガイは、草屋根の上など水辺以外にも生息していたため、朝露などの水滴に感染型幼虫であるセルカリアが含まれている可能性もありました。
この恐ろしさを象徴する言葉として、当時は「朝露踏んでも 地方病」ということわざが語られていました。農民たちは、素足で草むらを歩くだけで感染するという現実に、為す術がなかったのです。
地域の力で挑んだ70年
ミヤイリガイが中間宿主と判明して以来、「地方病の撲滅はミヤイリガイの撲滅に直結する」という認識が広まり、地域住民による殺貝活動が本格化しました。
1914年には硫酸や火による殺貝実験が行われましたが、効果的な方法は見つかりませんでした。そうした中、農民たちは自発的にミヤイリガイを手作業で採取し、県からは奨励金も支給されました。1917年からの8年間で、約96俵分に相当するミヤイリガイが採取されましたが、繁殖力の強さゆえ根絶には至らず、より効果的な対策が求められました。
1924年、内務官僚出身の本間利雄が山梨県知事に就任し、広島での成功事例をもとに生石灰による殺貝法を導入しました。この方法は京都帝国大学の藤浪鑑により考案されたもので、高い効果が確認されていました。藤浪を招き、甲府盆地での散布が始まりましたが、有病地の面積は広島の16倍以上に及び、作業は大規模かつ困難を極めました。
それでも1925年には「山梨地方病予防撲滅期成会」が発足し、県民からの多額の寄付により対策費用が賄われました。その後も、生石灰に加え、石灰窒素、火炎放射、天敵の導入、PCP薬剤の使用、水路のコンクリート化など、多様な方法が取り入れられ、行政と住民が一体となって70年以上にわたりミヤイリガイの撲滅に取り組みました。
戦後の日米共同研究
1944年、フィリピンのレイテ島で多くの米兵が日本住血吸虫症に感染したことをきっかけに、アメリカはこの病気に関心を寄せました。1947年にはGHQの衛生部隊が山梨県に入り、甲府駅に臨時研究所「保健車」を設置。地元研究者と連携して調査・啓発活動を展開しました。
この共同研究は、キャンプ座間に拠点を置く米陸軍第406総合医学研究所の主導で9年間にわたり行われ、殺貝剤「Na-PCP(ペンタクロロフェノールナトリウム)」の開発と実用化に成功しました。
その後、環境被害が発生したことから「ユリミン」「B2」などへの切り替えが進み、1960~1987年の間に大量の薬剤が使用されました。
甲府盆地の水路のコンクリート化
甲府盆地では、水路のコンクリート化も有効な対策のひとつでした。1936年、生物学者・岩田正俊が水路の直線化・コンクリート化による流速の増加でミヤイリガイの生息を抑えられると提案。しかし当時はセメントが高価で広範囲の施工は困難でした。
しかし、佐賀県での実験結果を受け、1948年に飯野村で試験施工が開始され、1956年から本格的な事業が国の支援を受けて始まりました。
コンクリート化の利点としては
- 土中のミヤイリガイの埋没・駆除が可能
- 毎秒61cm以上の水流で卵が流され定着できない
- 水路内の状況が目視しやすくなり、殺貝作業の効果が向上
最終的に、甲府盆地内の水路はすべてコンクリート化され、1996年の撲滅事業終了時には、その総延長は2,109キロメートルに達していました。
これは北海道函館市から沖縄県那覇市までの直線距離に相当します。
社会の変化と感染者の減少
水路のコンクリート化と並行して住民による地道な殺貝・消毒作業が進められました。その成果は新規感染者の減少という明確な形で表れ、1960年代から1970年代にかけて、住血吸虫卵の陽性率やミヤイリガイの感染率は急速に低下し、1980年代以降は検出例がゼロとなりました。
この新規感染者減少の背景には、以下のような複合的な要因がありました。
1. 土地利用と農業形態の転換
戦後の産業構造の変化により、水田から果樹園への転換が進みました。特にモモやブドウなどの果樹栽培が広がったことで、水を張り続ける必要がある水田が減少し、ミヤイリガイの生息環境が縮小しました。これには県の指導や地方病撲滅運動の後押しもあり、農民たちも地方病との決別のために果樹栽培への転換を受け入れました。
2. 農業の機械化
農作業の機械化により、ウシなどの家畜が激減し、感染源となる糞便由来の虫卵の発生が減少しました。また、堆肥から化学肥料への転換も、感染リスクの低下に寄与しました。
3. 合成洗剤の普及
昭和40年代には家庭からの合成洗剤を含む排水が水路に流れ込んでおり、排水に含まれる成分が偶然にも感染源であるセルカリアを死滅させる効果を持っていたことが確認されました。この「垂れ流し状態」が予期せぬ形で地方病対策に効果を発揮しました。
対策の負の側面
1. 生態系への影響
日本住血吸虫やミヤイリガイの撲滅を目的とした対策により、無関係な生物も影響を受けました。例としては殺貝剤の使用や河川のコンクリート化などにより、ミヤイリガイに似たカワニナ(ホタルの幼虫の餌)が減少し、それを食べるゲンジボタルも個体数を大きく減らしました。
1930年に天然記念物に指定されていた昭和町のホタル発生地は、1976年に指定解除されてしまいます。
一度は消えたと思われたホタルですが、1987年に再び確認され、翌年には住民団体「昭和町源氏ホタル愛護会」が結成されるなど町を挙げた保護活動が行われています。
2. 臼井沼の埋立て
山梨県中央市(旧田富町)にあった臼井沼(湿地)は、ミヤイリガイの温床として知られていました。1970年代も感染ネズミが多く確認され、効果的な駆除が困難だったため、地元住民による総決起大会の決議により1976年に埋立てが決定。
これに対し野鳥保護団体や学会は保存を訴えましたが、最終的に県議会で埋立てが正式決定されました。跡地は甲府リバーサイドタウンや山梨県流通センターとして開発されました。
嘆願から115年、ついに終息宣言へ
1978年を最後に甲府盆地では新たな感染者が確認されず、ミヤイリガイのセルカリア感染個体や哺乳類の感染も1980年代初頭を境に見られなくなりました。1985年には抗体陽性者の平均年齢が60歳を超え、新たな感染が長期間確認されていないことが明らかとなりました。
1990年代に児童生徒4,249名を対象に行われたELISA検査(免疫反応を利用した抗体検査)でも全員が陰性。これらの結果を受け、1995年に山梨県の諮問機関が「地方病の流行は終息した」と報告。
1996年2月19日、山梨県知事が公式に地方病の終息を宣言しました。1881年の旧春日居村からの嘆願以来、115年にわたる地方病との長い闘いが、ついに終結を迎えた瞬間でした。
後世への伝承
ただし、ミヤイリガイは完全に撲滅されたわけではなく、再流行の可能性(輸入感染など)はゼロではありません。現在も山梨県ではミヤイリガイの生息調査や児童の検診が継続されています。また、研究用として日本住血吸虫とミヤイリガイは一部施設で飼育されており、診断用抗原製造に活用されています。
日本は住血吸虫症のメカニズムを世界で初めて解明し、撲滅に成功した唯一の国です。山梨県では、2005年に県立博物館で「地方病」コーナーが設けられ、2010年には旧杉浦医院を活用した資料館も開館。道徳教科書や学校の授業、NHKの教育番組でも取り上げられ、撲滅の歴史と教訓を次世代に伝える取り組みが行われています。
まとめ:忘れてはならない「地方病」の記憶
かつて甲府盆地を中心に多くの人々の命と暮らしを蝕んだ「地方病(日本住血吸虫症)」は、医学・科学・行政・地域社会の力が結集し、長い年月をかけて克服されました。感染源の撲滅という前人未到の挑戦を成し遂げた背景には、数えきれないほどの試行錯誤と、地道な啓発活動、そして何より「終わらせたい」という地元住民たちの強い願いがありました。
桃の花が咲き誇る春の甲府盆地は、「桃源郷」とも称されるほどの美しさで訪問者を魅了します。
その美しい景色の裏には、かつて壮絶な病との闘いがあったのでした。
参考リンク
- Wikipedia 地方病 (日本住血吸虫症) : https://w.wiki/E9kW
※本記事は、Wikipediaを参考にし、CC BY-SA 4.0ライセンスのもとで要約・再構成しています。
オリジナルの全文はWikipediaの該当ページにてご確認いただけます。
著作権およびライセンスについてはクリエイティブ・コモンズ 表示-継承ライセンスに準拠しています。
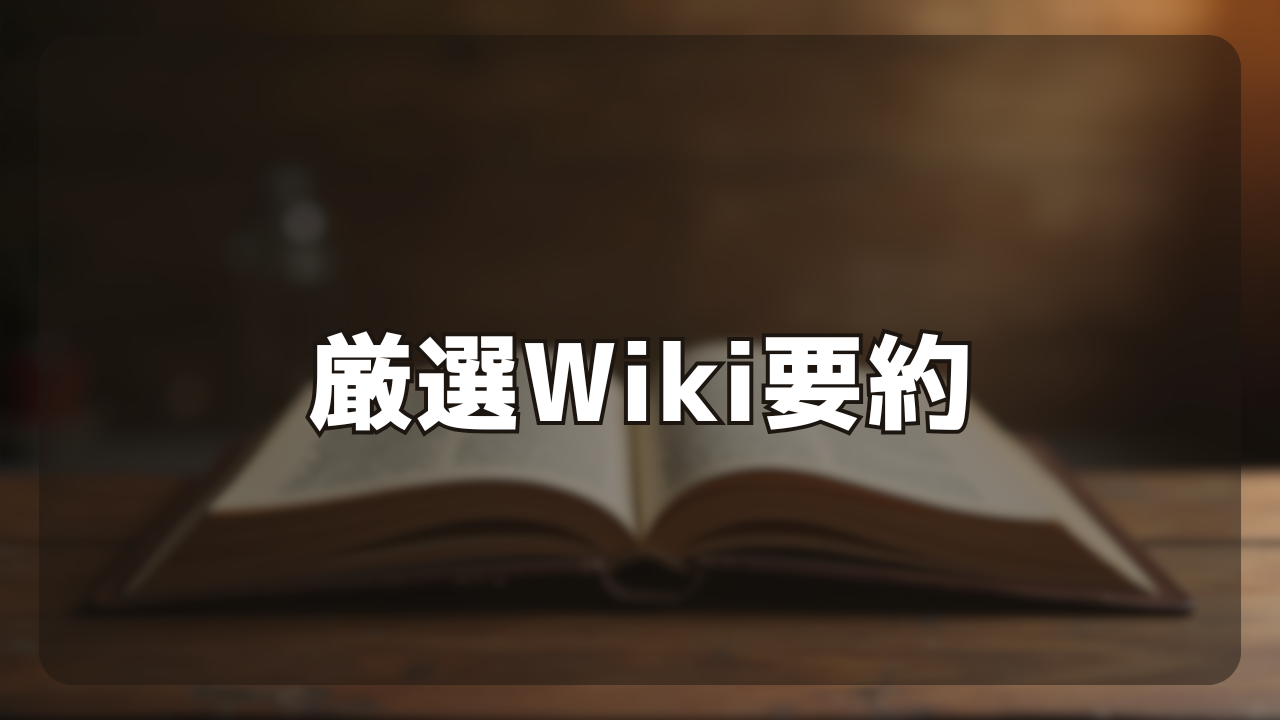
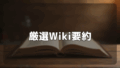
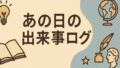
コメント