前回の記事では、日本の家庭用電圧が「なぜ100Vなのか」という背景を紹介しました。実はこの“低電圧”を採用している意外な国が他にもあります。それがアメリカです。
今回は、アメリカが120Vを選んだ歴史的背景から、日本が100Vを維持し続ける理由までを、わかりやすく解説します。
アメリカの家庭用電圧が120Vである理由
エジソンによる「直流100V」の採用
アメリカの電力システムの始まりは、トーマス・エジソンによる直流(DC)送電方式でした。1882年にニューヨークで運用が始まったパール・ストリート発電所では、白熱電球の性能と安全性を考慮し、約110Vが採用されました。
直流では距離が延びると電圧が自然に低下してしまうため、発電所では110〜120Vで供給し、利用者側で100V前後になるように設計されていたのです。
交流(AC)移行後も「120V前後」を維持
後に、ニコラ・テスラとジョージ・ウェスティングハウスが交流方式(AC)を普及させます。交流方式は長距離送電に優れており、現在の標準となりました。
しかし、当初の電気機器や照明器具は直流100Vを前提に設計されていたため、交流に移行しても110〜120Vの電圧帯が維持されました。この「既存設備との互換性」が現在まで続いているのです。
安全性とインフラの維持
120Vはヨーロッパの230Vに比べると感電リスクがやや低く、安全性の面でも有利とされています。加えて、すでに全米に広がった電気インフラや製品設計を変更するのは極めて高コストであるため、120Vの維持が選ばれ続けています。
補足:実は「120V × 2」で240Vも使える
アメリカの住宅には、120Vの電線が逆位相で2本引き込まれており、これを組み合わせることで240Vの機器にも対応できます。乾燥機やIHクッキングヒーター、エアコンなどの大型家電は、この240Vを利用しています。
なぜ日本は100Vを維持しているのか?
日本でも200Vの電源は存在し、エアコンやIHクッキングヒーターなどで一般的に使われています。しかし、家庭用の標準コンセントは今も100Vが基本です。
では、なぜ世界の多くの国が200V以上を採用している中で、日本は100Vのままなのでしょうか?
それは、変えたくても変えられない現実があるからです。
日本が100Vを維持している主な理由
❌ 莫大なコストと改修の負担
- 電力インフラ全体の改修
- 家庭やビル内部の配線の交換
- 家庭用電化製品のすべてを買い替え
❌ 技術的な課題と安全基準の見直し
- 全国の建物内配線を一斉に変更するのは、技術的に非常に困難
- 100Vは感電リスクが低く、家庭での安全性に優れている
- 電圧を上げれば、コンセント・ブレーカーなどの規格再設計が必須
❌ 社会的混乱と生活への影響
- 家電の大量廃棄と買い替え需要
- 改修工事による長期停電や社会混乱
- 高齢者や非IT層への説明・サポートの負担
これらを全国規模で行うとなると、国家予算規模の費用と個人の大きな負担が発生します。
社会全体に大きな混乱をもたらす可能性が高いため、100Vの維持が最善策とされています。
まとめ:100Vは“選んだ”のではなく“最適化された結果”
日本の電力システムが100Vを採用し続けているのは、単に他国に合わせなかったわけではありません。初期に導入されたインフラや安全基準、そして経済合理性の観点から、100Vという選択が最も現実的だったのです。
「変えられなかった」背景には、技術、経済、社会、そして安全性といった複数の要素が複雑に絡み合っています。
たとえ不便に感じることがあっても、現在の100Vは、日本の現状において最もバランスの取れた選択肢だと言えるでしょう。
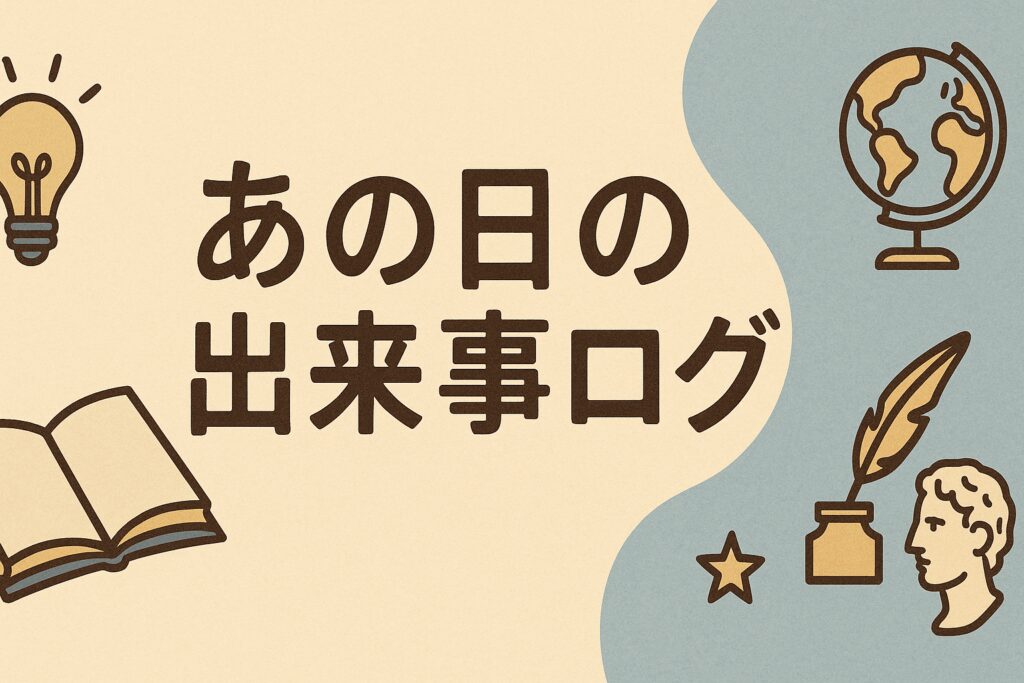
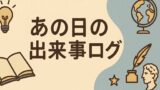
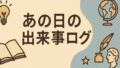

コメント