1957年の世界初の人工衛星スプートニク打ち上げは、冷戦下での「威信」をめぐる競争を一気に激化させました。
その衝撃の中で、米国とソ連はいずれも“月での核爆発”による圧倒的なパフォーマンスを検討しました。米側の Project A119 は1958–59年にかけて米空軍特殊兵器センターの依頼で作成された機密研究です。計画の骨子や関係者、報告書の存在については当時の調査報告書が公開されており、A119自体が実在したことは確認されています。
Project A119(米国)
発端と目的
ソ連の先行に対し、地球から肉眼でも「月上の閃光」を見せることで政治的・心理的な勝利、すなわち「ショック・アンド・オー(圧倒的な威圧)」を演出しようという考えが発端でした。名目上は「月面での爆発を科学的に観測して月面物理を調べる」ことが掲げられていましたが、実際にはプロパガンダ効果が強く意識されていたことが記録から読み取れます。
研究体制と主要人物
1958年にイリノイ工科大学に小規模な研究チームが組織され、レオナルド・レイフェルが中心になって報告書「A Study of Lunar Research Flights(Vol. I)」をまとめました。
若手研究者として後に著名な天文学者となるカール・セーガンも、月の塵の挙動や爆発の可視性に関する計算・理論の一部にかかわっていました。セーガン自身は後にこの計画に倫理的な懸念を抱き、月面汚染のリスクを警告した一人でもあります。
技術的想定
報告書では「どの種類の核弾頭を使うか」「落下や失敗時のリスク」「月面爆発が地球からどう見えるか」などが検討されました。議論の中で小型核弾頭 W25(公称で1.7キロトン程度)が現実解として候補に挙がっていたという資料的裏付けがあります。
リスク評価と中止
打ち上げ失敗で核弾頭が地球に落下する危険、月面環境(永久的に放射能汚染される可能性)や将来の科学探査への悪影響、国際的非難の可能性などが重視され、最終的に採用されませんでした。こうした判断は、報告書そのものとその後の関係者証言で確認できます。
Project E-4(ソビエト)
構想の位置づけ
ソ連側にも「E」系列という月関連の計画群が存在し、E-1が到達、E-2/E-3が周回撮影などを想定する中で、E-4が「月面での核爆発」の検討にあたる段階だったと伝えられます。これは当時の内部文書・回想録や、冷戦後に公開された資料・研究で整理されています。
出典と信頼性
E-4に関する一次的な体系書類は米側のA119ほど大量に公開されてはいませんが、ロケット工学者 ボリス・チェルトックの回想録(Rockets and People)や歴史研究者の整理により、そのような検討が実際に存在したことが示唆されています。噂として報じられた段階から中央委員会提出の記録まで、当時の「虚実」が混在している点に注意が必要です。
国際条約への影響
こうした「宇宙での核爆発」の企図は、冷戦の緊張緩和と科学探査の保護を求める国際世論に影響を与えました。
- 1963年 部分的核実験禁止条約(PTBT): 大気圏・宇宙・水中での核実験が禁止され、月面核爆発の実行は法的に不可能となりました。
- 1967年 宇宙条約(Outer Space Treaty): 天体(月を含む)への核兵器の配備やその他の大量破壊兵器の設置が制限され、宇宙空間の平和利用が国際的な規範として確立されました。
これらの条約は、A119やE-4のような考え方が国際的な規範へ反映され、宇宙の軍事化を食い止めるための重要な防波堤となりました。
仮説 — もし実行していたら、何が起きたか?
実行されていた場合、短期的・長期的に複数の影響が考えられます。
1) 「見える」政治的効果は一時的にあったかもしれない
弾頭が予定通り月面で爆発し、地球上から閃光や一時的な反射が観測できれば、冷戦期のプロパガンダには一定の効果があった可能性があります。ただし、その「勝利」は科学的・倫理的反発を招き、国際的孤立を招くリスクも高いでしょう。HISTORY
2) 科学・探査への深刻な害(長期的影響)
月面の一部が放射能で汚染されれば、ロボット探査・有人探査の計画は後退します。放射性物質は月面に長期間残留し、科学サンプルの汚染や将来的な基地建設の安全性に影を落とします。これにより「宇宙探査の進展」が数十年単位で遅れた可能性があります。
3) 地球側のリスク:落下・放射性拡散の可能性
ロケット失敗や軌道制御ミスで核弾頭が大気圏再突入・地上落下した場合の被害は甚大です。さらに、上層大気での爆発や碎片による広域汚染は当時の監視・救援体制では対応困難で、国際問題が発生します。こうした「事故リスク」が実行をためらわせた主因の一つでもあります。
4) 技術的に“成功”しても得られる科学的知見は限定的だった
月は大気がないため爆発の光や塵の振る舞いは地上観測で得られる情報が限られます。得られる科学的利益に対して、倫理・環境コストが大きすぎた可能性が高いです。
5) 国際法・軍事情勢への波及
もし一方の超大国が敢行していたら、もう一方が「報復的」または同様の実行を図った可能性があります。結果として宇宙の軍事化が一層進み、現在のような条約形成(PTBT、宇宙条約)の流れが変わったかもしれません。現代における宇宙兵器禁止の枠組みは、こうした過去の企図を踏まえて構築されてきた面があります。
まとめ
A119とE-4は、「できるかもしれない」ことと「して良いこと」は別であるという冷戦期の一断面を教えてくれます。科学的好奇心と軍事的発想が交差したとき、倫理・環境・国際協調の視点を欠くとんでもない選択肢が生まれうるという警鐘です。
現代の宇宙活動(月や小天体の資源利用、宇宙兵器化の議論)を考える上で、これらの過去の計画は重要な歴史的教訓となっています。

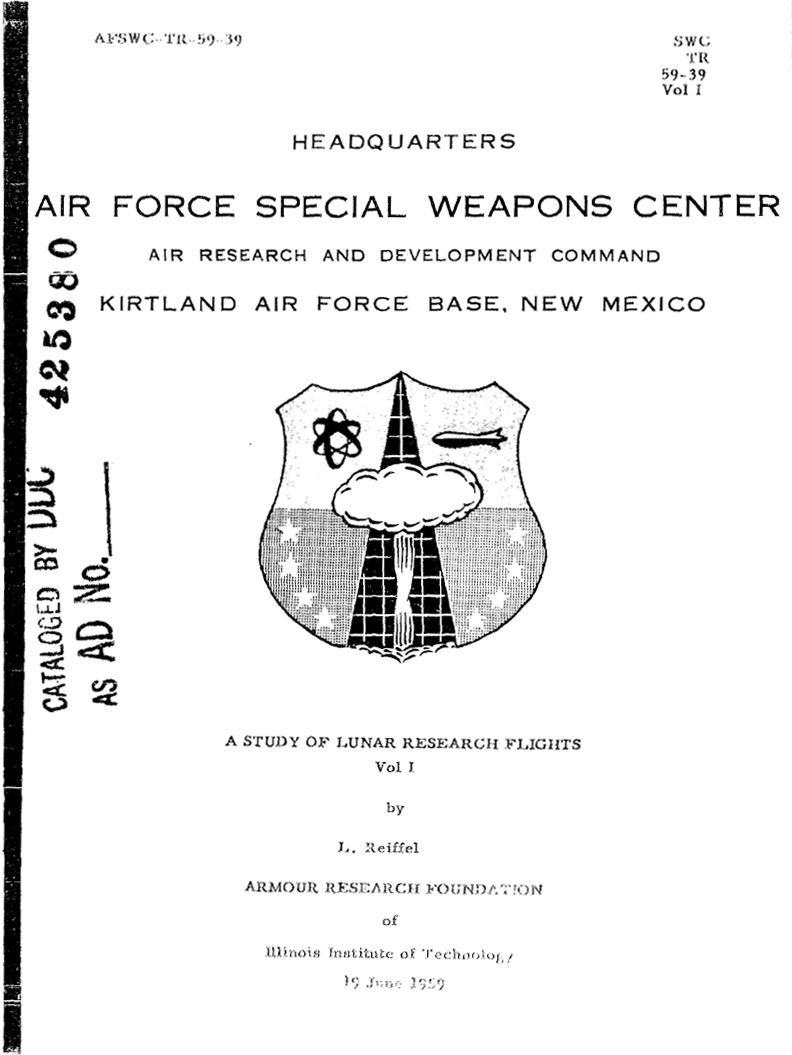


コメント